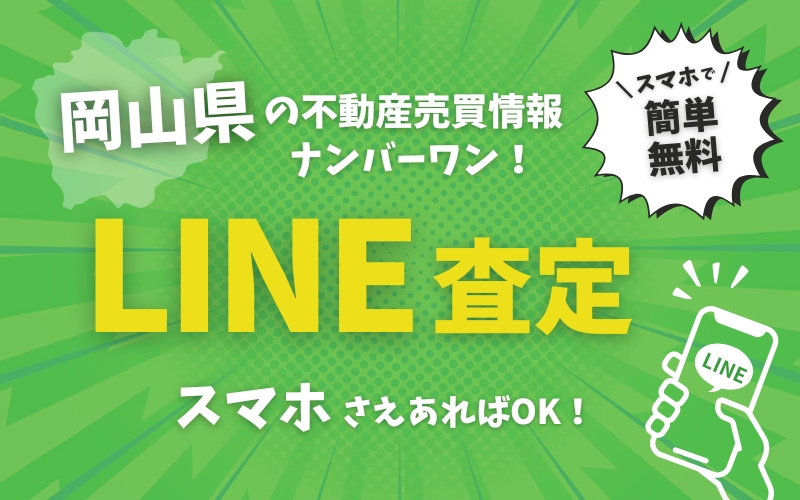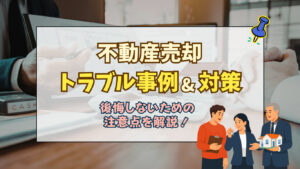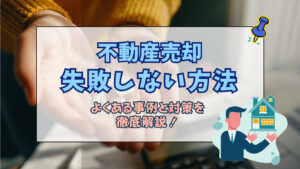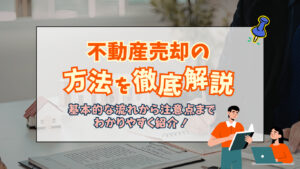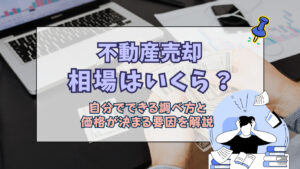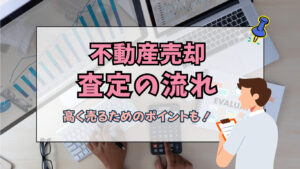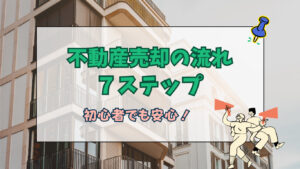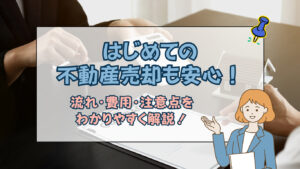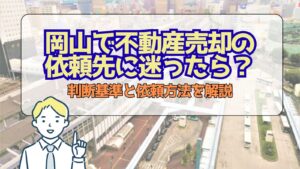市街化調整区域の家・土地を売却するには?売れない理由と成功させる4つの方法を解説
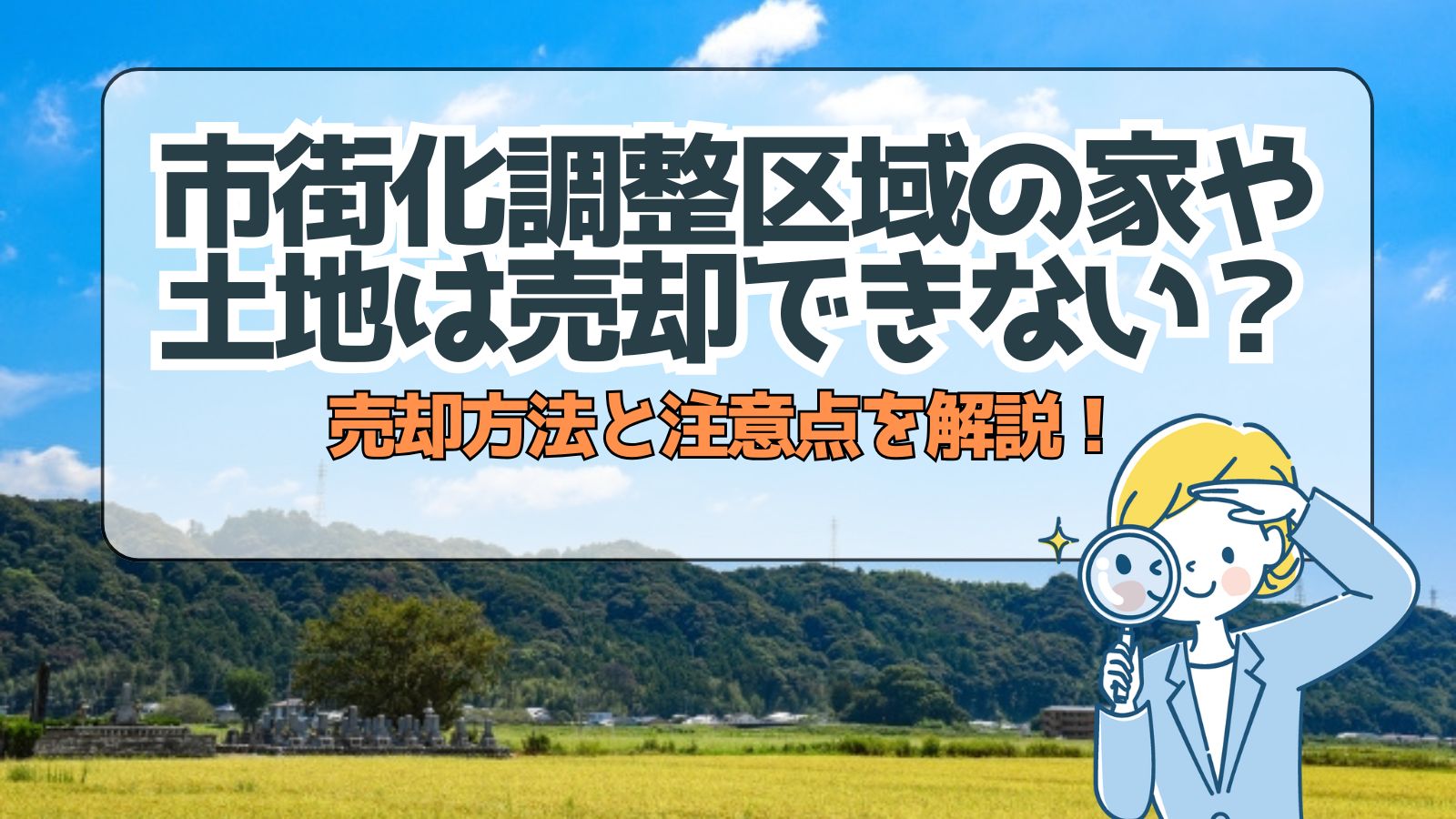
市街化調整区域にある家や土地の売却を考えていても、「どこから手をつければよいのか分からない」「制限があると聞いて不安」と感じる方は多いのではないでしょうか。
まずは、市街化調整区域とはどのような場所なのかを理解することが、売却を前向きに進めるための第一歩となります。
本記事では、市街化調整区域の基礎知識に加え、売却方法や注意点、買い手となる人の特徴などについて詳しく解説していきます。市街化調整区域での不動産売却を成功させるヒントとして、ぜひお役立てください。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る
市街化調整区域とは?基礎知識と市街化区域との違い

市街化調整区域は名前だけを聞くと分かりづらいですが、その成り立ちや役割を知ることで「なぜ建築が制限されるのか」「なぜ売却しにくいと言われるのか」といった疑問がクリアになります。まずは、市街化調整区域がどんな目的でつくられたのか、その基本から押さえていきましょう。
市街化調整区域の目的
市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大(スプロール現象)を防ぎ、農地や森林といった自然環境を守ることを目的に指定された区域です。この区域では、原則として新たな建物の建築や宅地開発が厳しく制限されており、住宅や商業施設の建設には自治体の許可が必要となります。
土地の用途が限定されることから、一般的な市街地と比べて売却が難しいとされることもありますが、条件や使い方次第では売却の可能性も十分にあります。まずはその仕組みを正しく理解することが重要です。
市街化調整区域と市街化区域の違い
市街化調整区域の特性をより深く理解するためには、対となる「市街化区域」との違いを知っておくことが大切です。
市街化調整区域と市街化区域は、都市計画法に基づいて設定され、それぞれ異なる目的と特徴を持っています。両者の違いを表にまとめました。
| 項目 | 市街化調整区域 | 市街化区域 |
| 目的 | 市街化を抑制(自然環境の保護) | 市街化を促進(都市開発) |
| 開発・建築 | 原則禁止(許可が必要で制限が厳しい) | 自由に開発・建築が可能 |
| インフラ整備 | 不十分な場合が多い | 整備が進んでいる |
| 土地利用の自由度 | 制限あり | 高い |
市街化調整区域の物件が売却できないと言われる理由5つ

市街化調整区域が売却しづらいと言われるのには、買い手が不安に感じるいくつかの理由があります。主な理由を5つ解説していきます。
1. 新築や建て替えに制限がある
市街化調整区域では、新たな住宅の建築や建て替えを行う場合に自治体の許可が必要です。この制限があるために、購入希望者が「自由に家を建てられない」と感じ、検討しづらくなることが最大の理由です。特に新築には都市計画法の制限がありますが、既存の住宅の建て替えは認められるケースも多いです。ただし、ルールは自治体ごとに異なるため、事前の確認が必須です。
2. 住宅ローン審査が通りにくい
市街化調整区域の物件は、居住や建築に制限があるため、住宅ローンの審査が一般的な物件と比べて慎重に行われる傾向があります。金融機関によっては、担保評価の難しさや流動性の低さを理由に、融資の対象外とするケースも見られます。ただし、すべての金融機関で難しいわけではなく、頭金の割合が多いなど条件付きでローンが利用できる場合もあります。
3. 生活インフラが整備されていない
市街化区域に比べて、道路の整備状況や、電気・ガス・水道といった生活インフラが整っていない場所もあることが、買い手から敬遠される理由です。都市ガスではなくプロパンガスになる地域や、下水道が整備されていないため、汲み取り式トイレや浄化槽の設置が必要な地域も少なくありません。
4. 農地の場合は転用許可が必要
市街化調整区域内の農地は、そのままでは宅地として利用できません。農地を宅地などに変えるための「転用許可」を得る手続きが必要であり、これには時間やコストがかかるため、売却のハードルが高くなります。手続きが煩雑なため、行政書士など専門家に依頼することが多くなり、その分の費用もかかります。
5. 周辺環境が整っていない
市街化調整区域の物件は、交通の便や周辺施設の充実度といった面で、市街化区域と比べて利便性が低いことがあります。日常の買い物ができる商業施設が少なかったり、学校や病院といった公共施設へのアクセスが不便な地域も少なくありません。特に子育て世代や高齢者のいるご家庭にとっては、生活利便性に不安を感じる要因となります。
市街化調整区域の物件を売却する4つの方法

市街化調整区域にある物件でも、売却がまったくできないわけではありません。物件の特性や地域の事情に合わせて、適切な方法を選ぶことが、スムーズな売却につながります。
1. 市街化調整区域の売却に詳しい不動産会社に依頼する
市街化調整区域の売却は通常の不動産取引と違い、複雑なプロセスや専門知識が必要です。そのため、売却成功のために最も重要になるのが不動産会社選びです。市街化調整区域専門の不動産買取業者や、そのエリアに密着した不動産会社に依頼することで、売却がスムーズに進む可能性が高まります。
2. 空き家バンクに登録する
空き家バンクとは、主に自治体が運営している空き家のマッチングサービスで、地方への移住促進が目的です。一般的な不動産サイトではなかなか届かない層、特に地方移住や古民家暮らしに関心を持つ人々にアプローチできる点が大きなメリットです。ただし、自治体ごとの登録基準や審査条件があるため、事前に確認が必要です。

3. 個人売買で売却する
友人や知人、または個人売買専門のサイトを利用して、個人間で売買する方法もあります。仲介手数料がかからないというメリットがある一方で、以下の注意点があります。
- 専門的な手続きや責任をすべて売主自身が負うことになる。
- 住宅ローンの審査が通らない場合がある。
- 売却時や売却後にトラブルが発生することがある。
少しでも不安がある場合や、法律・契約に自信がない場合は、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
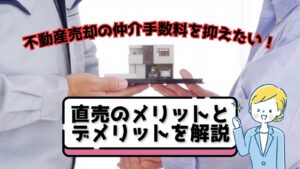
4. 隣地の所有者へ交渉する
隣地の所有者は、自分の土地を広くできる、開発許可が下りれば親子で同じ敷地内に住めるなど、購入メリットが明確です。買い手側にとっても利用価値が高い場合が多く、境界線をめぐるトラブルにもなりにくいため、売却がスムーズに進む可能性があります。
市街化調整区域の物件を売却する相手は?

市街化調整区域の物件には様々な制約が課されるため、売却する相手も限定されます。ターゲット層を絞って売却活動を行うことが、スピーディな売却への第一歩です。
本章では、市街化調整区域の売却相手として候補に挙がるのはどのような人かを解説していきます。
農業や林業を営んでいる人
農業や林業を営んでいる人は、市街化調整区域の適した買い手です。なぜなら、農業や林業を行うために必要な住宅や施設と判断される場合、開発許可を得られる可能性が高くなるからです。市街化調整区域の物件は相場価格が低いので、開発許可さえ得られれば買い手にとってもメリットと言えますが、開発許可を得るためには一定規模で事業を行っている証明が必要となります。
市街化調整区域内の事業者
市街化調整区域内にある事業者も、売却相手として候補に挙がります。近くで事業を営んでいる人が、資材置き場や来客用の駐車場として活用したいと購入するかもしれません。売却したい物件の周辺で商売をしている人がいれば、一度声をかけてみるとよいでしょう。
隣地の所有者
隣地の所有者に売却を交渉してみるのもおすすめです。買い手側にとっても隣の土地が手に入れば自分の土地を広くでき、開発許可が下りれば家を建てて子どもや孫と同じ敷地内に住むこともできます。隣地の所有者が購入するならば境界線をめぐるトラブルにもなりにくく、売却がスムーズに進むメリットもあります。
地方の中古住宅を探している人
地方の中古住宅を探している人も、市街化調整区域の物件に関心を持つ可能性があります。田舎でのスローライフや自然に囲まれた暮らしを求めている層です。特に近年は、古民家をリノベーションして自分好みに暮らすスタイルが若い世代にも広がっており、需要が少しずつ高まっています。
このようなライフスタイルを重視する層にとっては、新築や建て替えに制限があるといった市街化調整区域ならではの条件も、大きな障壁とはならない場合があります。そのため、物件の魅力や活用方法をしっかり伝えることで、購入につながる可能性も十分にあると言えるでしょう。
市街化調整区域の物件を売却する際の注意点
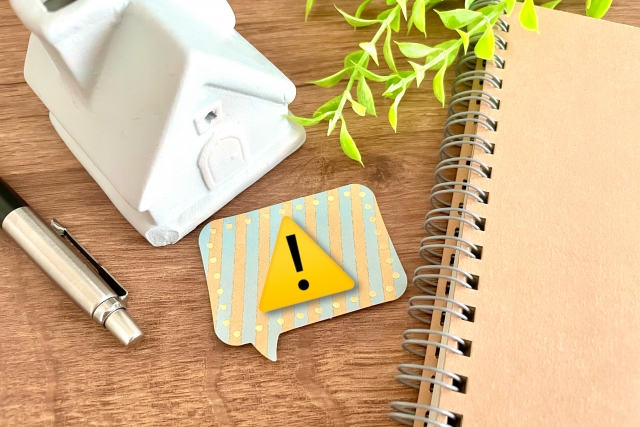
市街化調整区域の売却には、通常の土地売却とは異なる点があります。特に注意しておくべき点について解説します。
1. 売却する土地の地目を確認する
地目(ちもく)とは、土地の登記簿上で定められた利用目的の分類です。
- 農地の場合: 売却には農地転用の許可が必要になります。
- 山林・原野の場合: 宅地への用途変更が必要になります。
地目によって売却の可否や条件が異なるため、必ず確認しておきましょう。
2. 自治体の区域指定を確認する
市街化調整区域内でも、自治体の条例や都市計画によって、さらに細かい指定がなされていることがあります。買い手は土地の利用条件や建築の可否を重要視していますので、建築や用途変更に関する正しい情報を買い手に伝えることで安心感を与えられ、売却がスムーズに進みます。
3. 建物の建築が「線引き」の前か後かを確認する
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「線引き」と言います。売却する物件が線引き前に建築されたのか、後なのかによって、売却条件が異なる場合があるため、確認しなくてはなりません。確認方法は、登記簿や都市計画図を見るか、自治体の窓口で直接確認できます。
4. 専門家に相談しながら売却を進める
市街化調整区域の家や土地を売却する際は、法的な確認や許認可が必要になる場面が多いため、専門的な知識を持つ不動産会社への相談が欠かせません。特に、都市計画法や自治体ごとの条例に詳しい不動産会社や、地元密着型の不動産会社を選びましょう。一つひとつ確認を重ねながら慎重に進めることが成功の鍵です。
まとめ
市街化調整区域にある家や土地の売却は、通常の不動産売却とは異なり、法的な制約や手続きの複雑さが伴うため、不安を感じる方も多いかもしれません。しかし、適切な知識と準備があれば、売却を成功させることは十分に可能です。
本記事では、市街化調整区域の基本的な仕組みから、売却が難しいと言われる理由、売却方法や買い手の傾向、さらには注意すべきポイントまで幅広く解説しました。制限があるからといって売却をあきらめる必要はありません。物件の特性に合ったターゲットを見極め、空き家バンクの活用や専門家の支援を受けることで、スムーズな売却へとつなげることができます。
まずは、所有している物件の用途や制限を整理し、どのような売却方法が適しているかを検討しましょう。そして、不明点や手続きに不安がある場合は、地域に詳しい不動産会社に相談することをおすすめします。正しい情報と信頼できるサポートが、納得のいく売却への第一歩となるはずです。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る