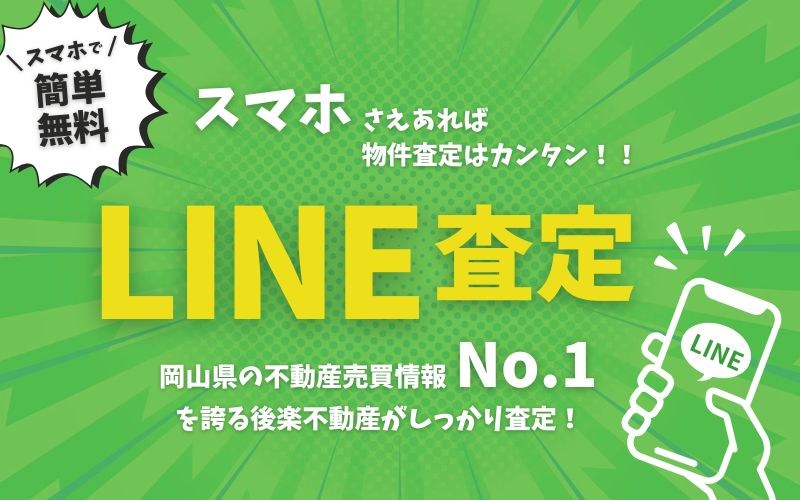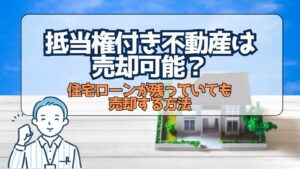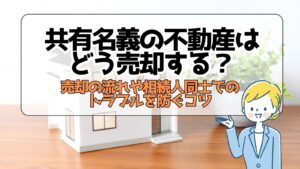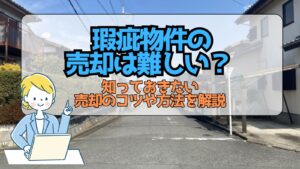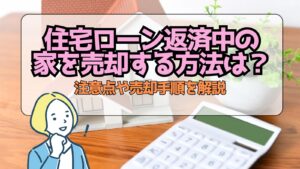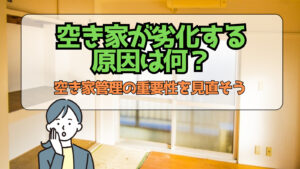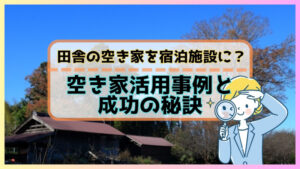不動産の相続における配偶者居住権とは?要件や手続き方法、活用したほうがいいケースについて解説
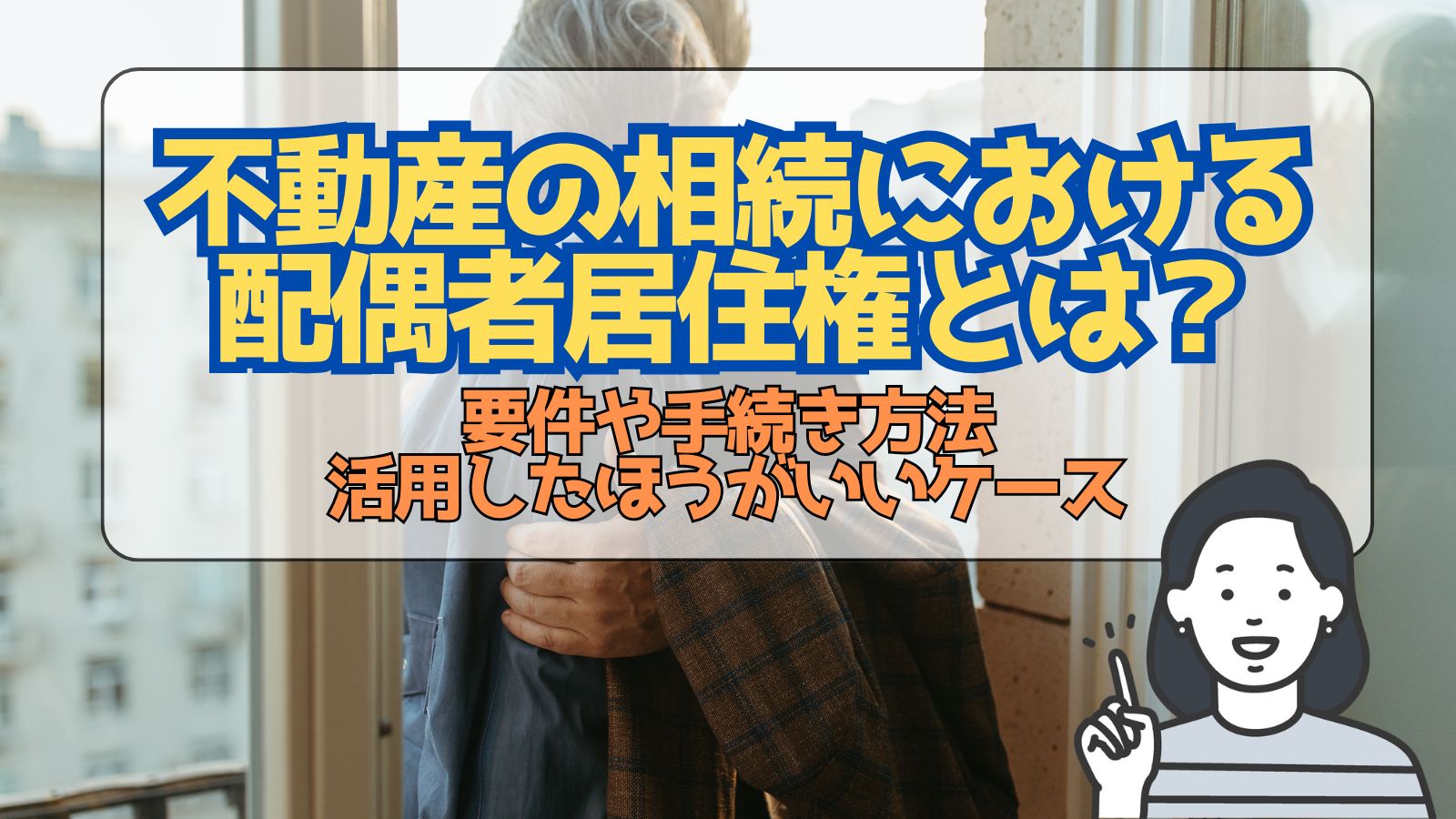
2020年の相続法改正により、「配偶者居住権」という制度が新たに導入されました。これは、夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者が住み慣れた自宅に無償で住み続けることを可能にし、生活の安定を図ることを目的とした制度です。
ただし、この制度を利用するには一定の要件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。そのため、相続時のトラブルを避けるためには、事前の準備が重要です。本記事では、配偶者居住権の制度概要、活用が適しているケース、具体的な手続きの流れについて詳しく解説していきます。
相続を控えている方や、相続対策を検討している方、不動産を含む遺産分割を進めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を監修した人

岩冨 良二
後楽不動産 売買事業部 係長
不動産業界歴26年のベテランで、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格を持つエキスパート。豊富な知識と実績でお客様から厚い信頼を得ており、売買事業部のエースとして活躍中。複雑な取引もスムーズにサポートし、最適な提案を行う頼れるプロフェッショナルでありながら、社内のムードメーカーとしても周囲を明るくする存在。
配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、夫婦どちらかが亡くなった後に、残された配偶者が亡くなった人の所有する建物に一定期間無償で居住できる権利のことです。この権利は、2020年4月1日以降に発生した相続から新たに認められるようになりました。
建物の価値は「所有権」と「居住権」に分けられるとし、残された配偶者が所有権を持たなくても一定の要件に該当すれば居住権を取得できるとする考えのもと、成立している権利です。配偶者居住権があることで、建物の所有権を持たない配偶者も今まで暮らしていた家にそのまま住み続けることが可能になります。
配偶者居住権が設定された経緯とは
高齢化が進んだことで、配偶者の死後に残された妻(もしくは夫)が長期間一人暮らしをするケースも増えてきました。しかしながら、法定相続分に従って子どもが自宅の所有権を取得すると、残された配偶者が退去を求められるというケースもあり、特に前妻の子や親族との相続争いで住み慣れた家を失うリスクも問題視されていました。
そこで、残された配偶者が無償で住み続けられる権利を設けることで、生活の安定を図り、相続人間のトラブルを軽減する目的で2020年に施行されたのが配偶者居住権です。
また、夫婦のどちらかが亡くなった際にただちに退去が必要となると、残された配偶者には精神的にも金銭的にも大きな負担となってしまいます。そのため、最低でも6か月間は無償で今の家に住み続けられる権利(配偶者短期居住権)も同時に導入されています。
配偶者短期居住権との違い
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、どちらも亡くなった配偶者の所有する建物に住み続けるための権利ですが、目的や期間が異なります。
| 配偶者短期居住権 | 配偶者居住権 | |
|---|---|---|
| 目的 | 相続発生直後の配偶者の生活を守る | 長期間にわたり配偶者の居住を保障する |
| 存続期間 | 遺産分割が確定するまで、または相続開始から6か月間 | 配偶者が亡くなるまで(または遺産分割で定めた期間) |
| 取得方法 | 法律上当然に発生(手続き不要) | 遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判で取得 |
| 費用 | 無償 | 無償 |
| 登記の可否 | 不可 | 可能 |
| 相続税の影響 | なし | 評価額が相続税の対象になる |
配偶者短期居住権は、相続開始直後に配偶者が住み慣れた住まいから突然退去させられることがないように、一定期間の無償居住を認める制度です。遺産分割協議や配偶者居住権の取得手続きが整うまでの間も、安心して住み続けられるよう保護する目的があります。なお、配偶者居住権が取得されると、その時点で短期居住権は消滅します。
配偶者居住権の消滅事由
以下のような場合は、配偶者居住権は消滅し配偶者は建物を返還する義務を負うことになります。
- 存続期間の満了
- 配偶者の死亡
- 居住建物の滅失
- 居住建物の所有権を取得した場合
- 配偶者が居住権を放棄した場合
- 居住建物所有者からの消滅請求
配偶者居住権は配偶者が亡くなると自動的に消滅し、相続の対象にはなりません。また、配偶者が老人ホームに入居するなどの理由で居住権を放棄した場合も権利は消滅します。
他にも、配偶者が建物を適切に管理しない、無断で第三者に貸し出す、無断で改築するなどの違反行為があった場合は所有者が消滅請求を行うことができます。
配偶者居住権の要件と手続き方法
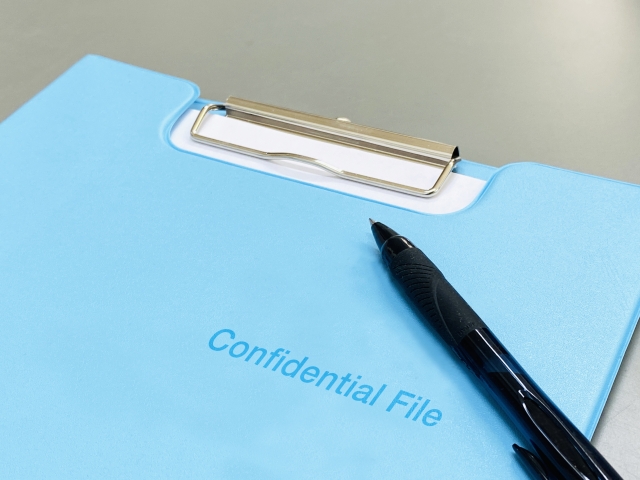
配偶者居住権を取得するためには、一定の要件を満たした上で適切な手続きを行う必要があります。
配偶者居住権の要件
- 法律上の配偶者であること
- 相続開始時に対象の建物に居住していたこと
- 遺言による遺贈、遺産分割協議、または家庭裁判所の審判で取得すること
配偶者居住権が認められるためには、法律上の配偶者であることが必要であり、内縁関係の配偶者は対象になりません。また、相続開始の時点で、被相続人が所有していた建物に実際に居住していたことが条件となります。
配偶者居住権は、相続が開始されたからといって自動的に発生するものではなく、遺言・遺産分割協議・家庭裁判所の審判のいずれかによって建物に対して配偶者居住権を設定する必要があります。
具体的には、被相続人が遺言で配偶者居住権の設定を明示していた場合や、相続人全員の合意による遺産分割協議で設定される場合があります。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立て、裁判所の判断によって配偶者居住権を取得することも可能です。
配偶者居住権の手続き方法
- 遺産分割協議を行う
- 家庭裁判所の審判を利用する(必要な場合)
- 登記手続きを行う
- 税務申告を行う
配偶者居住権の取得の際には、相続人間での話し合いにより配偶者居住権を設定するかどうかの決定がなされます。なお、遺言がある場合はその内容に従います。相続人間で合意が得られない場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。
配偶者居住権が取得できたら、なるべく早く登記手続きを行いましょう。登記手続きは、該当の建物がある地域を管轄する法務局で行います。
また、配偶者居住権は相続税の課税対象となるため、適切な評価を行い申告しましょう。
配偶者居住権と相続税の関係

配偶者居住権は相続財産の一部として評価され、相続税の対象になります。配偶者居住権は所有権よりも評価額が低くなるため、相続税の負担を軽減できる可能性があることも設定するメリットのひとつです。
相続開始後10か月以内に税務署へ申告が必要で、配偶者居住権の評価額を含めた相続税額を計算し、納税することとなります。
評価方法
配偶者居住権の金額(評価額)は、「建物の価値」と「配偶者があと何年住み続けると想定されるか(平均余命)」の2つを元に計算されます。
まず、建物の価値は「固定資産税評価額」という金額を使います。これは、毎年市町村から送られてくる固定資産税の通知書に書かれている金額です。
次に、「あと何年住むことになりそうか」という年数に応じて、金額を割り引いて(将来の価値に直す)計算します。これは「複利現価率」という計算式を使いますが、細かい計算は税理士や専門家に任せるのが一般的です。
たとえば、建物の固定資産税評価額が1,000万円で、配偶者の平均余命が16年とされた場合は、0.623という割引率(複利現価率)を使って次のように計算されます:
この場合、配偶者居住権の評価額は約623万円となり、この金額が相続税の計算対象となります。
二次相続への影響
配偶者居住権は一次相続時に配偶者の生活を守るために有効です。しかし、二次相続時には分割されていた建物の評価額が元の建物全体の価値に戻るため、所有権の評価額が上昇し相続税の負担が増える可能性があります。
子どもなどの相続人は、予想以上の税負担を強いられる場合があるため注意が必要です。
配偶者居住権を設定するメリットとデメリット

本章では、配偶者居住権を設定することでどのようなメリットとデメリットがあるのかを解説していきます。
メリット①:住み続ける権利を確保できる
配偶者居住権を設定すると、被相続人の所有する自宅に無償で住み続けることが可能になります。高齢の配偶者が新しい住居を探す負担を軽減し、精神的・経済的な安定を得られます。
また、相続人とのトラブルを防ぎ、住み慣れた環境で安心して暮らせる点が大きなメリットです。特に、相続財産の大半が自宅の場合、配偶者居住権を活用することで住居を確保しつつ、他の財産も適切に分割できます。
メリット②:財産分割が柔軟になる
配偶者居住権を設定すると、居住権と所有権を分けて相続できるため、財産分割の選択肢が広がります。例えば、自宅の所有権を子どもに譲り、配偶者は居住権を取得することで、預貯金などの資産を確保しやすくなります。
配偶者は生活資金を確保しつつ、住み慣れた家に住み続けることが可能になり、安心して生活できるでしょう。また、相続人間の公平な分割がしやすくなることで、遺産分割協議の話し合いがスムーズに進められます。
メリット③:相続税の節税効果がある
配偶者居住権を設定すると、建物の権利が「居住権」と「所有権」に分かれ、それぞれ別個に相続税評価が行われます。居住権の評価額は、建物の固定資産税評価額と配偶者の平均余命に応じた複利現価率を用いて算出されるため、通常は所有権よりも低くなります。
この評価方法により、建物全体を一括して評価するよりも相続財産の総額を抑えられる場合があり、結果として相続税の課税対象額が減少する可能性があります。たとえば、建物を相続する際に居住権と所有権を分けることで、配偶者は自宅に住み続けながらも現金などの資産を別途受け取る余地が生まれ、生活資金の確保や、他の相続人との公平な財産分割がしやすくなるといった実務上のメリットもあります。
ただし、配偶者が亡くなった後の二次相続では、消滅した居住権の分が所有権に戻り、建物全体の評価額が再び上昇します。そのため、二次相続で相続税が増加する可能性がある点には注意が必要です。短期的な節税効果だけでなく、将来的な税負担も見据えた相続対策を検討することが重要です。
デメリット①:売ったり貸したりできないので、お金に換えるのが難しい
配偶者居住権は、「住むための権利」なので、家を売ったり、人に貸したりすることはできません。つまり、自分の持ち物のように自由に使ったり、現金化したりすることができないのです。
たとえば、将来的に配偶者が老人ホームに入ることになり、自宅を売ってその費用にあてたいと思っても、居住権しか持っていないと家を売ることはできません。
また、自宅を担保にしてお金を借りる「リバースモーゲージ」などの金融サービスも、基本的には利用できません。そのため、配偶者居住権は安心して住み続けられる反面、「資産として活用しにくい」という点がデメリットになります。
デメリット②:修繕費や固定資産税の負担がある
配偶者居住権があると、その家に住み続けることはできますが、家の修繕や日常の管理、さらには固定資産税などの費用は原則として配偶者自身が負担する必要があります。
たとえば、雨漏りの修理や外壁の塗り替えなど、大きな修繕が必要になった場合でも、家の持ち主ではなくても費用は自分で出さなければなりません。
また、所有権がないため、家を売ってお金に換えたり、貸して家賃収入を得たりすることもできません。こうした維持費の負担が続くことで、生活費を圧迫する可能性がある点は注意が必要です。
デメリット③:登記が必要で手続きが複雑
配偶者居住権を取得しただけでは、「この家に住み続ける権利がある」ということを正式に証明できません。これを証明するためには、「登記」という手続きを法務局で行う必要があります。
登記をしていないと、後から家を売られたり、他の人が権利を主張した場合に、自分の居住権を守れなくなるおそれがあります。登記をしておけば、「この家に住む権利があります」と法律的に主張できるようになります。
ただし、この登記には書類の準備や法的な知識が必要で、手続きを自分だけで進めるのは難しい場合もあります。そのため、多くの方は司法書士などの専門家に依頼しますが、その分の費用(数万円〜十数万円程度)がかかる点が、ひとつの負担になるかもしれません。
配偶者居住権を活用すべき3つのケース

ここからは、配偶者居住権を活用すべきケースはどのような場合なのかについて解説していきます。配偶者居住権を設定すべきか迷っている方は、参考にしてみてください。
①相続財産の大半が自宅である場合
相続する財産のほとんどが自宅だけ、というご家庭は少なくありません。たとえば、現金や預貯金があまりなく、自宅だけが大きな資産という場合、相続人同士で「どう分けるか」が難しくなることがあります。
もし配偶者が家の所有権をすべて相続すると、他の相続人(たとえば子どもたち)には公平な分け前が届かず、不満やトラブルの原因になることも考えられます。
そんなときに配偶者居住権を活用すれば、「住む権利」と「所有する権利」を分けて相続することができます。たとえば、子どもが家の所有者となり、配偶者はその家に住み続ける「居住権」を持つことで、配偶者は住まいを確保しつつ、子どもには代わりに預貯金などの財産を分けるといった柔軟な対応が可能になります。
このように、家の価値が大きい場合でも、住む人と財産を分ける人を分けることで、家族全員が納得しやすい形の相続を実現できるのが、配偶者居住権の大きな利点です。
②配偶者が高齢で住み慣れた自宅から離れたくない場合
高齢の方にとって、長年暮らしてきた自宅はただの「建物」ではなく、生活のリズムや思い出がつまった大切な場所です。そうした住まいを手放して引っ越すことは、心にも体にも大きな負担になることがあります。
たとえば、相続によって家の所有権が子どもに移り、「家を売るから出て行ってほしい」と言われた場合、年齢を重ねた配偶者にとっては新しい環境に慣れるのも簡単ではありません。
こうしたときに配偶者居住権を設定すれば、家の所有者でなくてもそのまま自宅に住み続けることができます。しかも、基本的には亡くなるまで無償で住み続けられるため、住む場所を失う不安がなくなり、安心して老後を過ごすことができます。
特に、老人ホームへの入居を考えていない場合や、住環境の変化に不安を感じている方にとっては、心身の安定にもつながる大きなメリットです。
③相続人間のトラブルを避けたい場合
相続では、残された家族の間で「誰がどの財産を受け取るのか」が大きな問題になります。たとえば、子どもが「家は売ってお金にしたい」と考えている一方で、配偶者は「住み慣れた家にこれからも住み続けたい」と希望するケースでは、意見が食い違って話し合いがうまく進まないことがあります。
また、配偶者が家の所有権を全部受け取ることに、他の相続人(たとえば前妻の子どもなど)が不満を感じるケースも少なくありません。
こうしたときに配偶者居住権を設定することで、「住む権利」と「家の所有権」を分けて相続することができるようになります。つまり、配偶者は自宅に住み続けられ、他の相続人はその家の所有権や、代わりにお金など別の財産を受け取ることで、相続人どうしが納得しやすい形で分けることができるのです。
このように、配偶者居住権をうまく活用することで、家族の間のトラブルを未然に防ぐ手助けになります。
配偶者居住権についてのよくある質問と回答

配偶者居住権に関する制度は、まだ新しい仕組みであるため、具体的な運用方法や注意点について疑問を持つ方も多くいらっしゃいます。ここでは、実際によく寄せられる質問とその回答を紹介します。
- 配偶者居住権を設定すると、住宅ローンの返済義務はどうなりますか?
-
住宅ローンの返済義務は所有者にあります。配偶者居住権を取得しても、ローンの支払い義務は発生しません。
- 配偶者居住権を設定して、賃貸に出すことはできますか?
-
配偶者居住権は譲渡や賃貸ができないため、第三者に貸し出すことはできません。ただし、所有者の許可があれば可能な場合もあります。
- 配偶者居住権を設定して、登記しないとどうなりますか?
-
登記をしていないと、「この家に住み続ける権利がある」ということを他人に証明できません。たとえば、家の所有者がその建物を第三者に売ってしまった場合でも、登記があれば「自分には住む権利がある」と主張できますが、登記がなければ、その人に退去を求められてしまう可能性があります。
配偶者居住権を取得したら、なるべく早く法務局で登記を行うことをおすすめします。登記をすることで、第三者に対しても正当に居住を続けられる権利があることを守れるようになります。
まとめ
相続をきっかけに、住まいの将来や不動産の扱いに悩まれる方は少なくありません。特に、配偶者が引き続き自宅に住み続けられるのか、あるいは不動産をどう分けるべきかといった点は、家族間の大きな関心事となります。
配偶者居住権は、条件を満たせば有効に活用できる制度ですが、適用には一定の手続きや他の相続人との調整も必要です。また、相続税や将来の不動産活用にどのような影響があるかも、事前に検討しておくことが大切です。
相続対策として不動産の活用をお考えの方、また相続にともなう不動産の売却や分割に不安を感じている方は、岡山の地域事情に精通した後楽不動産にぜひご相談ください。専門知識と豊富な実績をもとに、お客様の状況に合わせた丁寧なサポートをご提供いたします。