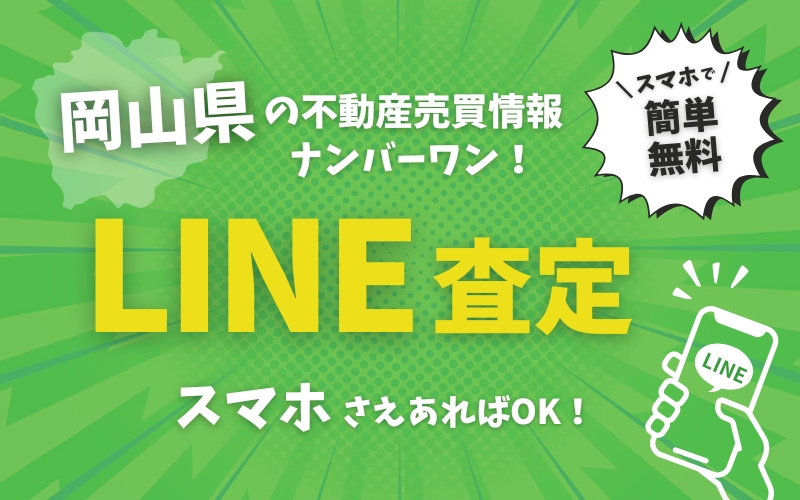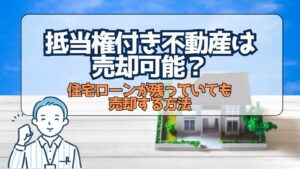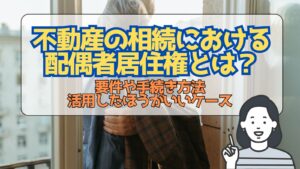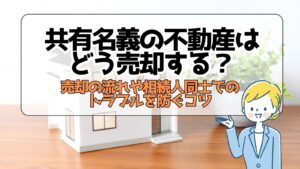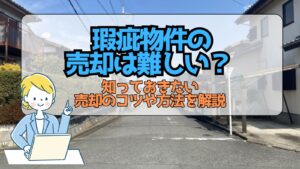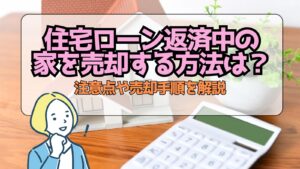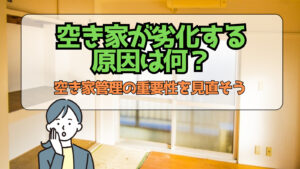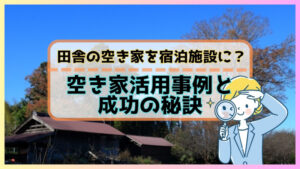相続した田舎の家はどうする?売却と相続放棄のメリット・デメリットを徹底解説

相続などで田舎の家を取得したものの、住む予定がなく、そのまま放置している方は多いのではないでしょうか。しかし、田舎の家を所有し続けると、経済的な負担だけでなく、管理や相続にまつわるトラブルなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。
田舎の家をどう整理するかは重要な課題です。本記事では、数ある選択肢の中から「売却」と「相続放棄」の2つに焦点を当てて解説します。どちらの方法も、それぞれのメリットとデメリットがあるため、自分に合った選択肢を見つけるための参考にしてください。
不要な田舎の家の処分方法を検討している方や、売却と相続放棄のどちらが適しているか迷っている方に向けて、具体的なポイントをお伝えします。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る
不要になった田舎の家を持ち続けることで生じるデメリットとは?

田舎の家を放置して持ち続けると、さまざまな問題が発生する可能性があります。これらの問題は、所有者自身だけでなく、子ども世代や近隣住民にも影響を及ぼす場合があり、適切な対策を取らないと将来的なトラブルを招く恐れがあります。
ここでは、田舎の家を持ち続けることによるデメリットを具体的に解説します。
「負動産」となるリスク
田舎の家は、人口減少や需要の低下によって市場価値が下がりやすく、売却が難しくなることで「負動産」となるリスクが高いとされています。「負動産」とは、所有しているだけで固定資産税や管理費用などの経済的負担が発生し続ける不動産を指します。
さらに、長期間所有し続けることで、次世代にまで負担を引き継ぐことになる可能性もあります。特に子ども世代が相続を避けたいと考えていても、事前に整理を進めていない場合、相続時の問題が複雑化することもあります。こうした負担を回避するためにも、不要な田舎の家は早めに整理を進めることが重要です。
維持費用の増加
田舎の家を所有している限り、固定資産税や管理費用といった維持費が発生します。加えて、空き家を放置していると定期的な清掃や修繕が必要になり、その費用が積み重なる点も見逃せません。
特に、管理が不十分な空き家は「特定空家」に指定されるリスクがあります。「特定空家」に指定されると、これまで適用されていた固定資産税の軽減措置が解除され、税額が大幅に増加する可能性があります。これにより、経済的負担がさらに増大するため、早急な対応が求められます。
遺産相続トラブルの可能性
相続時に遺産分割が必要な場合、相続人が複数いると話し合いが難航することがあります。また、相続人の中に認知症や判断能力が低下した人がいる場合、遺産分割や売却手続きが非常に複雑化します。
これらのトラブルを防ぐためには、相続が発生する前に家を整理しておくことが有効です。不要な田舎の家を持ち続けることで、相続時の手続きが煩雑になり、親族間の対立を招くリスクも高まります。
近隣住民への悪影響
老朽化した家を放置しておくと、建物の倒壊や外装材の飛散、害虫や害獣の発生といった問題が起こる可能性があります。これにより、周辺住民に迷惑をかけるだけでなく、最悪の場合、損害賠償請求を受けるリスクもあります。
また、放置された空き家は不法投棄や不法侵入の対象になることもあり、地域全体の治安や景観を損なう要因にもなります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、不要な田舎の家は適切に処分することが大切です。
田舎の家を手放すなら?相続放棄と売却の2つの選択肢

不要な家を手放す方法として、本記事では「相続放棄」と「売却」の2つの選択肢をご紹介します。それぞれの特徴とメリットを以下にまとめます。
相続放棄の特徴とメリット
相続放棄とは、相続が発生した際に、相続財産に含まれる資産や負債などの権利や義務を一切受け継がずに放棄することを指します。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行われ、相続放棄を行うと「最初から相続人ではなかった」と見なされます。
相続放棄のメリット
- 負債も含めて一切引き継がなくて済む
相続には不動産や預貯金といった資産だけでなく、借金やローンといった負債も含まれます。相続放棄を行えば、負債を肩代わりするリスクを完全に回避できるため、経済的な不安をゼロにできます。 - 単独で実行可能、他の相続人に左右されない
相続放棄は、自分の意思だけで手続きを進められるため、他の相続人の同意や調整を待つ必要がありません。相続人が複数いるケースでもスムーズに進められる点が大きな魅力です。 - 複雑な相続問題をシンプルに解決
負債が多い、共有名義が煩雑であるなど、複雑な相続問題が発生した場合も、相続放棄を選ぶことで一切の関与を避けられます。トラブルに巻き込まれる心配がなくなり、ストレスフリーな解決が可能です。
相続放棄は、負債リスクを完全に回避し、自分のペースで手続きを進められるシンプルで効果的な選択肢です。経済的な不安を減らし、複雑な相続問題から解放されるこの方法は、負担を抱えたくない方にとって非常に魅力的な解決策となるでしょう。
売却の特徴とメリット
不動産の売却とは、所有する土地や建物を手放し対価を受け取ることです。ほとんどの場合、不動産会社を介して買い手を探す「仲介」というやり方で売却は進められます。
仲介の他には、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」や、個人間で売買を行うケースもあります。
売却のメリット
- 不動産を現金化して次のステップに進める
売却によって、田舎の家を資産から現金に変えられるため、手元資金を活用する幅が広がります。リフォーム費用や他の投資、あるいは生活費に充てるなど、自由度の高い資金計画を立てられる点が大きな魅力です。 - 地域や市場に新たな価値を提供
売却された物件は、新たな所有者によって再び活用されることで、地域の活性化に貢献します。空き家が新しい住居やビジネスの場として生まれ変わることで、地域全体の魅力を高める一助となります。 - 売却方法の選択肢が多い
仲介による一般的な売却だけでなく、スピーディーに手放せる「買取」や、信頼できる個人間での売買も可能です。時間や条件、売却目的に応じて最適な方法を選べる柔軟性も大きなメリットです。
不動産売却は、現金化による経済的な安定を得るだけでなく、地域や市場へのプラスの影響をもたらす重要な選択肢です。ライフプランに合わせた売却計画を立て、田舎の家を価値ある資産として活用する第一歩を踏み出しましょう。
相続放棄と売却に共通するメリット
不動産の相続放棄と売却に共通するメリットは、以下のようなものがあります。
経済的負担の軽減
田舎の不要な家を手放すことで、固定資産税や管理費用といった経済的負担を軽減できる利点があります。2023年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、管理が不十分な空き家が「特定空家」に指定される可能性が高まりました。この「特定空家」に指定されると、それまで適用されていた固定資産税の軽減措置が解除され、税額が大幅に増えることがあります。
また、空き家の状態を最低限人が住めるレベルに保つためには、定期的な清掃や修繕などの維持管理費が発生します。将来的に利用する予定がある場合は管理が必要ですが、使用する意向がない場合にはこれらの費用が無駄になりかねません。そのため、適切なタイミングで売却や処分を検討することが重要です。
遺産相続トラブルに巻き込まれない
田舎の家を手放したい場合、その家を相続した相続人全員の同意が必要です。そのため、相続人が複数いる場合は、全員で意見を調整することが欠かせません。ただし、相続人の中に認知症や精神的な障害などで判断が難しい方がいる場合、意思確認や手続きを進めることが難しくなることがあります。
こうした場合、成年後見制度を利用するケースがあります。成年後見制度とは、判断能力が十分でない方の財産管理や法律行為をサポートするための仕組みです。家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人が選任されることで、その方の利益を守りながら売却や相続手続きを進めることが可能になります。ただし、この手続きには時間や費用がかかるため、相続が分かった時点で早めに相談や準備を始めることが重要です。
相続人全員で話し合いを進め、意見を調整することで、遺産分割に関するトラブルや手続きの遅れを防ぐことができます。必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談し、スムーズに手続きを進めることをおすすめします。
空き家問題で周囲に迷惑をかけないで済む
不要になった田舎の家を活用することなく放置していると、急速に老朽化が進んでいきます。老朽化した家は倒壊などのリスクがあり、周辺住民にも多大な悪影響を与えてしまう恐れがあります。
そのため、不要になった田舎の家を放置せず、売却等の適切な選択をすることで、問題の多い空き家として周囲に迷惑をかける心配もなくなるでしょう。
売却のデメリットは?

不要となった田舎の家を手放すことには多くのメリットがあることを説明してきましたが、売却時には考慮すべきデメリットも存在します。田舎の家をどう扱うのか、メリットとデメリットを考慮し慎重に検討していかなくてはなりません。
本章では、売却に伴うデメリットをリストアップし、詳しく解説いたします。田舎の家の売却を検討している際の判断基準としてご活用ください。
売却するための費用がかかる
家を売却する際には、仲介手数料をはじめとする諸費用や、税金などの費用が発生します。
- 仲介手数料
- 印紙代
- 譲渡所得税(不動産を売却して利益が出た場合)
- 測量費(境界が不確定な土地・戸建ての場合)
- 解体費
- ごみの処分料
仲介手数料は、不動産会社を介して売却した場合に発生します。計算式は以下の通りです。
家を解体し更地にしてから売却する場合は、解体費も必要です。一戸建て家屋の解体費用は、木造住宅だと1坪あたり3~4万円程度で、30坪の木造住宅の場合約90~120万円になります。
思い出のある実家を手放すことになる
田舎にあって誰も住まなくなったとはいえ、自分が生まれ育った思い出のある実家を手放すことは、つらいものです。家族の歴史を自分が途絶えさせてしまったような「罪悪感」や、実家がなくなることによる「喪失感」を感じてしまう人もいるでしょう。
さらに、親族の中に売却に反対する人がいれば、親族間での対立が生じるリスクもあります。実家を手放す際には、こうした心理的な苦痛や、親族間での軋轢が発生することも覚悟のうえで進めていかなくてはなりません。
売却までに時間がかかる場合がある
田舎にある家は、需要が限られているため、売却までに時間がかかるケースが少なくありません。不動産市場の動向や物件の条件によって売却までの期間は大きく異なり、数か月から1年以上かかる場合もあります。
売却に時間がかかると、その間にも家が老朽化し、物件の価値が下がる可能性があります。また、売却が完了するまでの間も固定資産税や管理費用といった維持費が発生する点に注意が必要です。
スムーズに売却を進めるためには、地元の不動産市場の動向を確認しながら、信頼できる不動産会社と相談し、売却活動を計画的に進めることが重要です。市場の状況に応じた適切な売却価格の設定や、必要に応じたリフォーム・修繕などの工夫が、売却期間の短縮に役立つ場合もあります。
物件によっては希望額で売るのが難しい
自分の親が苦労して建てた家を、二束三文では売りたくないと思うのは当然のことです。しかしながら、田舎の家は物件の築年数や状態・立地などによって、希望する金額での売却が難しい場合があります。
売却価格が建てたときにかかった金額の数分の一程度になってしまい、がっかりすることもあるでしょう。なるべく高く家を売却するためには、売却タイミングや市場の動向、物件の状態に合わせた計画を立てて行動することが大切です。
不動産会社に相談することで、現在の物件の価値が査定額として分かります。あらかじめどの程度の金額で売れるものなのか、希望額との差を把握しておくことをおすすめします。
相続放棄のデメリットは?
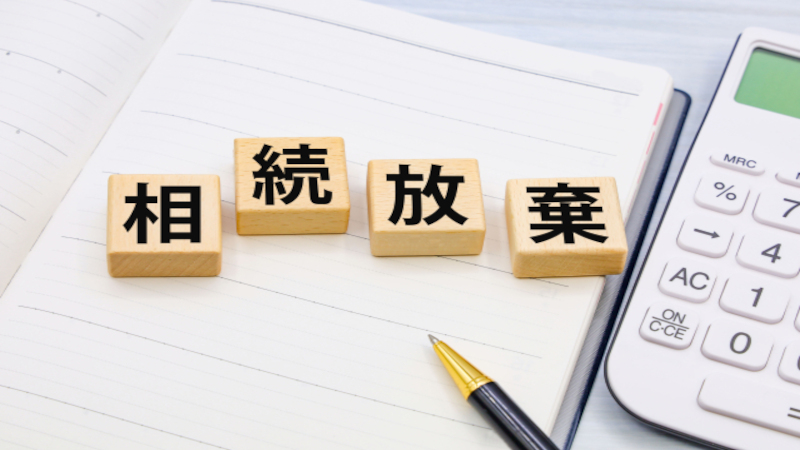
本章では、相続放棄を選択した場合のデメリットについて詳しく解説していきます。
プラスの財産も放棄する必要がある
相続放棄すると、被相続人の負債を相続しなくて済む一方、プラスの財産も相続できなくなります。本来相続できるはずだった資産も相続できなくなるため、経済的な損失が生まれる可能性があります。
田舎の家を相続したくないからといって相続放棄をすると、万が一不動産以外の資産があった場合、受け取ることができません。相続放棄する場合は、必ず相続財産の調査を行い、被相続人の資産と負債を把握し、十分に検討したうえで行いましょう。
相続放棄は撤回できない
相続放棄は基本的に一度行うと撤回することはできません。仮に後になって新たな遺産が発見された場合でも、相続放棄をした人はその遺産を受け取る権利を失います。
ただし、例外的に相続放棄の取り消しが認められるケースもあります。たとえば、詐欺や脅迫によって相続放棄を余儀なくされた場合や、未成年者が親権者などの同意を得ずに手続きした場合などが該当します。このような場合でも、家庭裁判所に申し立てを行い、手続きを経て取り消しを認めてもらう必要があります。
取り消しが認められるケースは非常に限られており、相続放棄をするかどうかの判断は慎重に行うべきです。事前に相続財産の内容をしっかりと調査し、必要であれば弁護士などの専門家に相談してから手続きを進めることをおすすめします。
手続きが複雑で費用もかかる
相続放棄を行うには、相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。期間内に必要な書類を準備し、申述する準備ができるのであれば、自分で行うことも可能です。
しかし、申述に必要な書類を揃えるのに時間がかかり、何の手続きもしないまま3か月の期限が過ぎてしまうと、以後の相続放棄手続きができなくなる可能性もあります。また、財産関係が複雑な場合や複数の相続人がいる場合も手続きが煩雑になり、法律に詳しくない人や忙しい人には手続きが難しくなります。
なお、司法書士や弁護士に相続放棄の手続きを依頼した場合の費用相場は、3~10万円程度です。
田舎の家を放置すると起こる問題点は?

田舎の家を放置していると、様々な問題が起こる可能性があります。問題点を把握しておくことでより適切な対処ができますので、どのような部分が懸念されているのか、整理しておきましょう。
外装や屋根の飛散、倒壊
空き家になった家は、住人がいた頃よりも早く老朽化が進行します。老朽化した家を放置していると、外装材や屋根材などが破損し、それらの部材が飛散や落下する危険性があります。
さらに老朽化が進むと、家自体が傾きはじめ地震などの際に倒壊してしまう恐れもあるでしょう。万が一、自分の家から飛散した物が原因で周辺の建物に被害を与えたり、通行人にけがをさせてしまったりした場合は、損害賠償が請求されるリスクもあります。
害虫や害獣の発生
田舎の家を放置していると、害虫や害獣が発生する可能性があるので注意が必要です。害虫や害獣が集まってくると、空き家の中で繁殖し糞や鳴き声で周辺住民に迷惑をかける場合があります。
- シロアリ
- ネズミ
- 野良猫
- スズメバチ
- ハクビシン
- アライグマ など
放置された家には、これらの害虫や害獣が集まりやすくなるため、定期的なメンテナンスや防除が必要です。
不法投棄や不法侵入の被害
空き家を放置していると、不法投棄のターゲットにされることがあります。家の庭などに粗大ごみや生ごみが投げ込まれ、害虫や悪臭の原因となり周辺住民に迷惑をかけてしまうような事態です。
また、日常的に管理されていない空き家は、空き巣被害に遭う可能性もありますし、放火・住み着き・犯罪の拠点として利用されるといったケースもあります。不法投棄や不法侵入を防ぐためには、定期的に空き家の見回りに行き点検する、空き家見守りサービスを利用するなどの対策が必要です。
周辺地域の不動産価値低下
老朽化した空き家は、倒壊の危険性や害虫害獣の発生、犯罪との関わりなどで周辺住民にも悪影響を与えます。空き家があることで景観も悪くなり、周辺地域にある不動産価値を低下させてしまう可能性もあるでしょう。
倒壊寸前の空き家が一軒でもあると、その地域全体のイメージ低下につながってしまいます。自分の所有する家が、近隣の住民にとって迷惑な存在にならないように、空き家と言えども手入れは怠らないようにしましょう。
相続放棄か売却、迷ったらどうする?

田舎の家が不要になった場合、相続を放棄するか、売却するかで悩むことがあるかもしれません。相続放棄と売却の選択は、相続する資産の状況や該当する不動産の特性、さらには田舎の家に対する個人的な感情などを総合的に考慮して決定する必要があります。
各物件や家庭の事情によって判断は異なりますが、一般的に考えられるケースについて、どちらの選択が適切かを整理しています。相続放棄か売却かの選択に迷った際の参考にしてください。
相続放棄をした方がいいケース
- 負債が多い場合
- 相続人が多い場合
- 心理的な負担が大きい場合
空き家に関するローンや税金などの負債が多い場合は、相続放棄を選べば負債を引き継がずに済みます。また、相続人が多い場合は、分割や共有に関するトラブルが予想されるので、相続放棄することで将来的なトラブルを回避できるでしょう。
田舎の家に対する感情的な負担が大きい場合は、相続放棄してしまうことで心の負担を軽減できることもあります。
売却したほうがいいケース
- 空き家の資産価値が高い場合
- 売却前のリフォームが可能な場合
- 不動産市場が好調な場合
空き家の資産価値が高い場合は、売却すればまとまった資金を得られます。他にも、売却前にリフォームができる資金がある場合、物件の価値を高めてより高く売却できる可能性があります。
不動産の市場が好調な場合や、周辺で中古戸建て物件のニーズが生まれている場合は、タイミングを逃さず売却のための活動を行うと良いでしょう。ただ、不動産市場の見極めやニーズの把握などは、不動産の業務に関わっている人でないと判断が付きづらいものです。
田舎の家の売却に向けて動き出す際には、信頼できる不動産会社に相談しながら進めていくと良いでしょう。
不要になった田舎の家は、価値が下がる前に行動を
本記事では、不要になった田舎の家をどう扱うべきか悩んでいる方に向けて、売却や相続放棄を含む選択肢のメリットとデメリットについて解説しました。生まれ育った田舎の家を手放す決断は簡単なものではありませんが、家の老朽化が進むと価値が下がり、最終的には空き家として周囲に迷惑をかけるリスクもあります。
ただし、田舎の家をどうするかは、家族の状況や経済的な事情、感情的な要素などによって最適な判断が異なります。売却や相続放棄が有効な場合もあれば、リフォームして再利用する、賃貸や別荘として活用するといった方法が適しているケースもあります。本記事で紹介した内容を参考にしながら、複数の選択肢を比較検討することをおすすめします。
もし売却を検討する場合は、早めに不動産会社に相談して市場動向を把握し、今後の計画を立てておくと良いでしょう。また、他の選択肢を考慮する際にも、専門家のアドバイスを受けながら進めることで、後悔のない最善の判断ができるはずです。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る