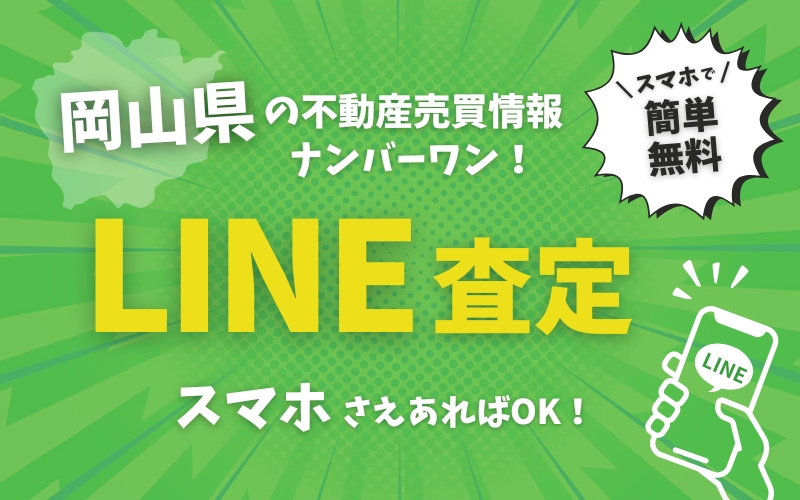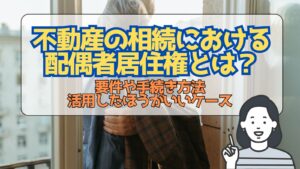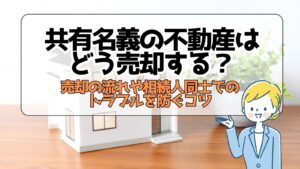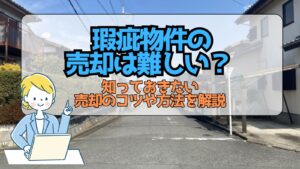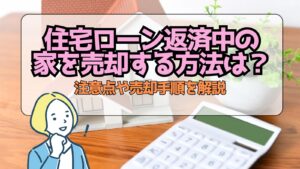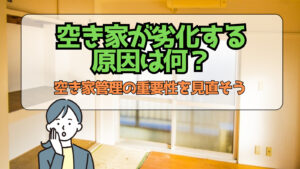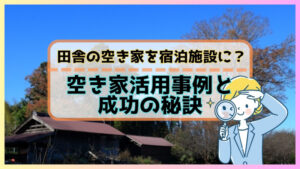抵当権付き住宅ローンのある不動産は売却できる?手続きと抹消方法を解説
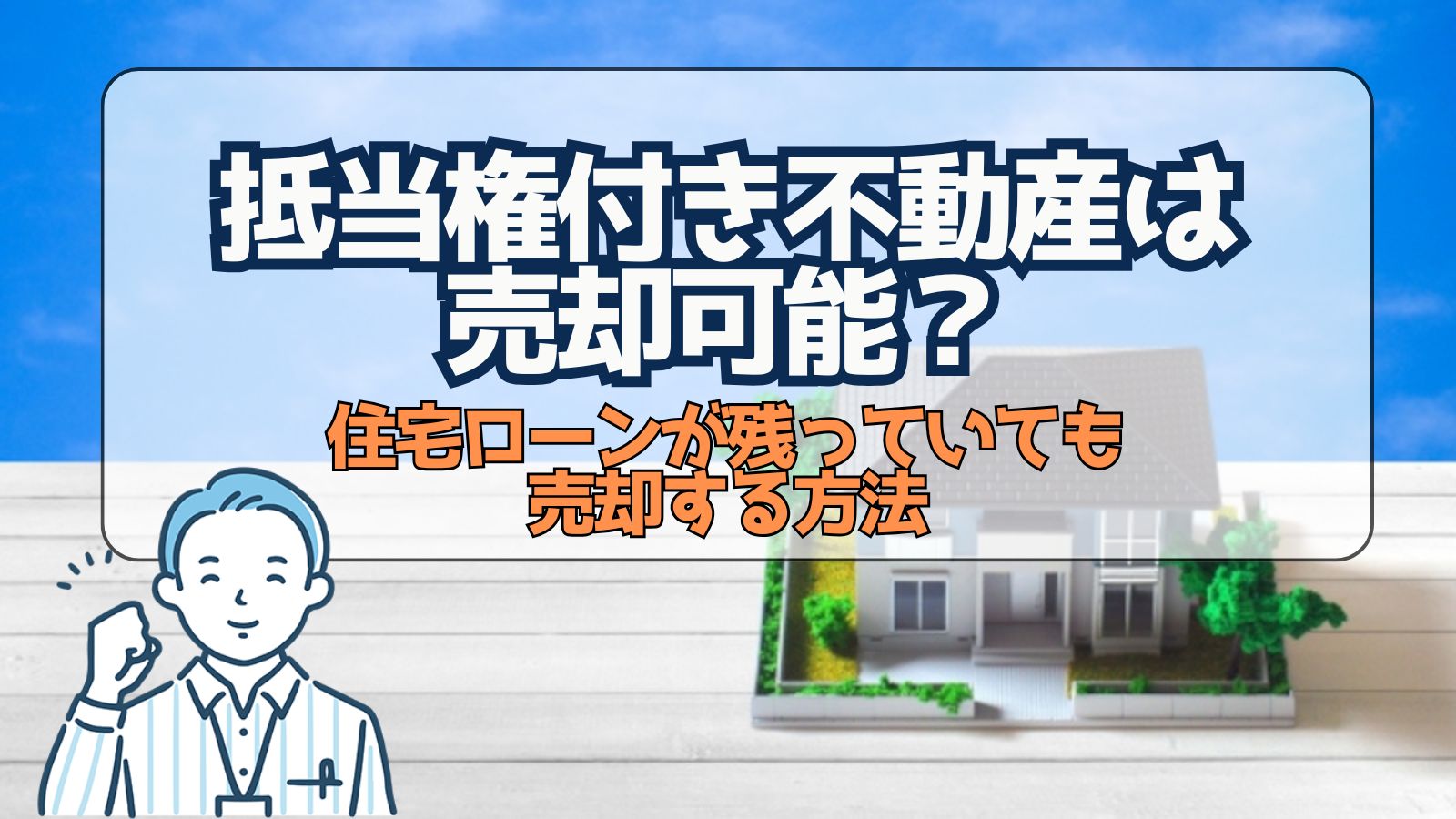
不動産を売却しようとしたとき、「この物件に抵当権は付いているのだろうか?」と不安になる方は少なくありません。住宅ローンが残っている不動産や、相続した物件には、抵当権が設定されているケースが多く、売却の進め方に注意が必要です。
抵当権が付いたままでは、原則として不動産を売却することはできません。そのため、売却を検討する際は、抵当権の仕組みや抹消方法をあらかじめ理解しておくことが大切です。本記事では、抵当権の基本から、抵当権付き不動産を売却する具体的な方法、相続時の注意点までをわかりやすく解説します。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る
抵当権とは?

このセクションでは、相続や売却を進めるうえで重要な「抵当権」について、基本的な仕組みや役割をわかりやすく解説します。
抵当権とは、金融機関などの債権者が、貸し付けたお金を確実に回収するために、不動産を担保として設定する権利のことです。もし債務者(お金を借りた人)がローンの返済を滞らせた場合、債権者はその不動産を競売にかけ、売却代金から貸付金を回収することができます。
抵当権の基本的な仕組み
抵当権は、債務者が土地や建物を担保にし、債権者がその権利を登記によって確保する仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設定対象 | 土地・建物などの不動産 |
| 設定者 | 債務者(ローンを借りる人) |
| 権利者 | 債権者(金融機関など) |
| 効力発生 | 登記によって第三者にも対抗可能 |
| 実行時 | 債務不履行時に競売などで回収 |
債務者がローン返済を滞納した場合、債権者は裁判所に競売を申し立てることができます。不動産が競売にかけられ落札者が決定すると、その売却代金から債権者が優先的に弁済を受けます。
抵当権は不動産を担保にしながらも債務者の生活を妨げず、債権者の回収リスクを抑える合理的な制度です。
住宅ローンと抵当権の関係
住宅ローンを利用する際、金融機関は貸付金の回収を確実にするため、購入する住宅に抵当権を設定します。返済が滞った場合、金融機関はその住宅を差し押さえて競売にかけ、貸付金を回収できる仕組みです。
抵当権は登記され、ローン完済後に抹消手続きを行うことで完全な所有権が借主に戻ります。住宅ローンと抵当権は切っても切れない関係にあり、借主は返済を続けることで徐々に真の所有者となっていきます。
抵当権付き不動産を売却する3つの方法

抵当権付きの不動産でも売却は可能です。ただし、買主が安心して購入できるように、売却と同時に抵当権を抹消することが一般的です。
本章では、抵当権付き不動産を売却する方法を3つご紹介します。
①手持ち資金で住宅ローンを完済して売却
②売却資金で住宅ローンを完済する
③任意売却を活用する
①手持ち資金で住宅ローンを完済して売却
この方法は、ローン残高が少ない方や十分な貯蓄がある方にとっては、最もシンプルで確実な売却方法です。売却前に自己資金で住宅ローンの残債を一括返済し、抵当権を抹消したうえで不動産を売却するため、買主にとっても安心感があります。
特に、売却活動を急がずに進めたい場合や、買主との交渉を有利に進めたい場合に有効です。
手持ち資金で住宅ローンを完済して売却の流れ
金融機関のマイページや窓口で、現在の残債額と繰上返済にかかる手数料を確認します。
金融機関に繰上返済の申し出を行い、返済日や金額を確定します。
ローン完済後、金融機関から「抵当権解除証書」など必要書類を受け取り、法務局で抹消登記を行います。
抵当権が抹消された状態で売却活動を開始します。
買主と契約を結び、引き渡しを行います。
売却時点で不動産に抵当権が存在しないため、買主との信頼関係を築きやすく、交渉もスムーズに進みます。
手持ち資金で住宅ローンを完済して売却のメリット
この方法の最大のメリットは、売却活動を自由に進められる点です。抵当権がない状態で売却できるため、買主にとってリスクがなく、購入意欲を高めやすくなります。
また、急いで売る必要がないため売却のタイミングや価格設定を柔軟に設定でき、より高値での売却が期待できます。さらに、ローンに関する煩雑な手続きを避けられるため、売主の負担が軽減できるのもメリットです。
資金に余裕がある方にとっては、最もストレスの少ない売却方法といえるでしょう。
手持ち資金で住宅ローンを完済して売却する際の注意点
まず、まとまった資金があることが前提の方法なので、手元に資金がない場合は選択できません。資金が用意できる場合でも、売却に時間がかかるとその間資金を動かせないのもリスクです。
完済後に資金繰りが苦しくならないように、計画的に売却活動を行う必要があります。
②売却資金で住宅ローンを完済する
この方法は、不動産の売却代金を使って住宅ローンの残債を完済し、同時に抵当権を抹消するというものです。売却前に手持ち資金でローンを完済する必要がないため、資金に余裕がない方でも実行しやすいのが特徴です。そのため、最も多く選択される方法になります。
売却代金から諸費用(仲介手数料や登記費用など)を差し引いた額が、ローン残高を上回る、または同程度である場合に有効です。
売却資金で住宅ローンを完済して売却の流れ
現在の住宅ローンの残債と繰上返済に必要な費用を金融機関に確認します。
不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を把握します。ローン残高よりも高く売れるかを試算します。
売却代金でローンを完済する旨を金融機関に相談し、抵当権抹消を「決済当日に実施」する旨の同意を得ます。
不動産会社と媒介契約を結び、買主が見つかったら売買契約を締結します。この時点ではまだ抵当権は残っています。
売却代金の中から残債を金融機関へ支払い、同時に抵当権の抹消登記と所有権移転登記を行います。司法書士の立ち会いが一般的です。
決済当日に抵当権抹消と所有権移転を同時に行う段取りがスムーズにいくように、調整しましょう。
売却資金で住宅ローンを完済して売却のメリット
この方法の最大のメリットは、手元資金がなくても売却を進められる点です。住宅ローンの残債が売却価格でまかなえる場合、自己資金を用意する必要がなく、資金的な負担を抑えられます。
また、抵当権を抹消した状態で引き渡しができるので、買主にとっても安心感があり、売却成立の可能性が高まります。さらに、売却益が出た場合はそのまま資金として活用できるため、住み替えにもつなげやすいという利点もあります。
売却資金で住宅ローンを完済して売却する際の注意点
売却価格がローン残債を下回る場合、売却してもローンを完済できない「オーバーローン」と呼ばれる状況になります。オーバーローンの場合は、差額を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て任意売却になる可能性があります。
決済当日に全ての手続きを同時に行うことになるため、不動産会社や司法書士とのスケジュール調整や連携が重要です。また、売却益が出た場合は譲渡所得税の課税対象となる場合もありますので、税務面の手続きについても事前に確認しておきましょう。
③任意売却を活用する
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債権者(金融機関など)の同意を得て不動産を売却し、その代金をローンの返済に充てる方法です。法的手続きに入る前の段階で行われることが多く、自己破産などの債務整理を回避する手段としても活用されます。
任意売却を活用する場合の流れ
住宅ローンの返済が困難になり、滞納が続くと「期限の利益」を喪失し、債権者から一括返済を求められる状況になります。
不動産会社や弁護士、司法書士など任意売却に詳しい専門家に相談し、売却の方針を決定します。
債権者に対して任意売却の意向を伝え、売却価格や残債の処理方法、引越費用の扱いなどについて合意を得ます。
通常の不動産売却と同様に買主を募集し、売買契約を締結します。
売却代金でローンを返済し、抵当権を抹消。残債がある場合は分割返済などの交渉を行います。
債権者との合意形成をいかに早く確実に進めるかが成否の分かれ目です。
任意売却を活用するメリット
任意売却は市場価格に近い金額で売却できるため、競売よりも残債を減らせる可能性があります。また、競売と異なり公告や入札が不要なため、プライバシーを保ったまま売却を進められるのもメリットです。
自己破産や強制的な競売に比べると、自主的に残債の整理ができるため、心理的なストレスが少なく済むのもメリットでしょう。
任意売却を活用する際の注意点
任意売却を行う場合は、ローンの滞納が前提条件にあるため、信用情報に傷が付くという点がデメリットです。それにより一定期間ローンの借入やクレジットの利用が制限される可能性があることは、念頭に置いておく必要があります。
また、債権者の同意が必要であることと、競売の申し立てが進行している場合は任意売却の猶予期間が限られるため、迅速な対応が求められる点にも注意しておきましょう。
抵当権抹消とは?手続きの流れと必要な書類・費用

抵当権抹消とは、住宅ローンなどの返済が完了した後に、不動産に設定された抵当権を登記簿から正式に削除する手続きのことです。原則として不動産の所有者(住宅ローンの債務者)が自ら行う手続きですが、書類作成や登記申請についての知識が必要なため、司法書士に依頼することが一般的です。
本章では抵当権抹消に必要な書類や、かかる費用などについて詳しく解説していきます。
抵当権抹消の手続きに必要な書類
- 登記申請書
- 登記識別情報または登記済証
- 登記原因証明情報(弁済証書や解除証書)
- 抵当権者の委任状
抵当権を抹消するには、法務局に対して登記の申請を行う必要があります。その際に必要となる主な書類は以下のとおりです。
登記申請書
抵当権抹消のための申請書です。法務局のホームページで様式をダウンロードでき、自分で作成することも可能ですが、不備があると申請が受理されないため、不安がある方は司法書士に依頼するのが安心です。
登記識別情報通知書または登記済証(権利証)
これは不動産の所有者であることを証明する書類です。通常、不動産を取得した際に交付されたものですが、紛失している場合は、法務局に「事前通知」や「本人確認情報による申請」などの方法で代替する必要があります。
登記原因証明情報(弁済証書または解除証書)
住宅ローンの完済や借入契約の終了を証明する書類で、通常は金融機関が発行します。抵当権設定の原因が解消されたことを登記上明らかにするために必要です。
抵当権者の委任状
抵当権者(通常は金融機関)が抵当権抹消登記を申請することを登記義務者(所有者)に委任したことを証明する書類です。弁済証書などと一緒に、金融機関から渡されるのが一般的です。
抵当権抹消にかかる費用
- 登録免許税:不動産1件に付き1,000円
- 登記事項証明書取得費:不動産1件に付き480~600円
- 司法書士報酬:約2~3万円
- 郵送費・印紙代など:数百円程度
抵当権抹消手続きは、自分で行うと実費のみで数千円程度に抑えられますが、司法書士に依頼する場合は2~3万円+実費が相場です。申請手続きは専門的な知識が必要で、書類の不備や記載ミスがあると法務局で受理されないこともあります。
司法書士に依頼すれば、ミスなく確実に手続きを進めてもらえて、自ら動く必要もありません。手続きを迅速に進めたい方や、安心感を重視する方は、司法書士に手続きを依頼するとよいでしょう。
相続不動産に抵当権が付いていた場合の対処法

不動産の売却を検討している中で、相続により取得した物件に抵当権が設定されていたというケースも少なくありません。このような場合、売却を進める前に、まずは不動産に関する権利関係や債務状況を把握することが必要です。
抵当権が付いているということは、その不動産がローンなどの借入れの担保となっている状態であり、相続によって不動産を取得した際には、その債務も含めて相続している可能性があります。相続時にはこうした抵当権に気付かず、後から登記簿を確認して存在を知るというケースも多いため、注意が必要です。
売却をスムーズに進めるためには、相続手続きと債務状況の確認を並行して行い、適切な対応を検討することが重要です。
まずは債務状況を確認する
不動産を相続した際には、まず登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、該当不動産に抵当権が設定されているかどうかを確認しましょう。抵当権がある場合は、あわせて債権者(金融機関など)や債権額の内容も確認することが重要です。
さらに、故人の通帳、ローン契約書、郵便物などを確認して借入先や借入金の残高を調べるとともに、関係する金融機関に照会を行いましょう。ローンの残債に加え、団体信用生命保険(団信)に加入していたかどうかの確認も必要です。
団信に加入している場合、被相続人の死亡によってローン残債が保険で完済されるケースがあります。ただし、契約内容や加入時の健康状態、保険の対象となる条件などによっては適用されない場合もあるため、必ず金融機関に詳細を確認することが大切です。
相続放棄という手もある
相続した不動産に抵当権が設定されており、債務が資産を上回る場合や、返済の見込みが立たない場合には「相続放棄」を検討することも一つの手段です。相続放棄をすると、その不動産を含む一切の財産や負債の相続を回避できます。手続きは家庭裁判所に対して申述を行う形で進められ、原則として「相続を知った日から3か月以内」に行う必要があります。
この方法には、借金を引き継がなくて済むという大きなメリットがありますが、同時にプラスの財産もすべて放棄することになります。また、一度放棄をすると原則として撤回はできません。こうした点を踏まえ、相続財産の内容をしっかりと確認したうえで判断することが大切です。
相続放棄をすると、次順位の相続人へと権利が移るため、親族間での事前の話し合いや調整も重要です。意図しないトラブルを防ぐためにも、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しながら、冷静に対応していきましょう。
債務を返済する方法
抵当権付きの不動産に家族や親族が居住している場合など、不動産を手放すのが難しい場合には、債務を返済して抵当権を抹消する必要があります。故人の預貯金や死亡保険金を使ってローンを完済できれば、抵当権は抹消できます。
団体信用生命保険に加入していれば、死亡によりローンが完済扱いとなる可能性もありますので、団信の適用条件を金融機関に確認しましょう。
不動産を売却して返済
不動産の評価額がローン残債を上回る場合は、売却代金で完済し抵当権を抹消することもできます。ただし売却には相続登記の完了が必要で、相続人間の協議も不可欠です。
登記や売却には相続人全員の同意が必要になりますので、相続が発生したらすみやかに相続人が集まり、今後の不動産の活用方針について検討するべきでしょう。相続した不動産の売却に関しては、不動産会社によるサポートを受けることをおすすめします。
相続から時間が経つほど、相続人が増えたり連絡が取れなくなったりという事態が増えてしまいます。相続が発生したら、すみやかに不動産の現況確認を行い、不動産会社に相談しながら今後の活用方針を決定していきましょう。

まとめ
抵当権が付いた不動産でも、状況に合った方法を選べば売却は可能です。売却を進めるうえで重要なのは、住宅ローンの完済と抵当権の抹消をどう行うかを事前に整理しておくことです。
また、相続した不動産に抵当権が付いている場合でも、返済・売却・相続放棄などの選択肢を冷静に検討することで、無理のない対応ができます。
まずは登記簿で抵当権の有無を確認し、売却を検討する場合は不動産会社や専門家に相談しながら進めると、安心して売却を進められるでしょう。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る