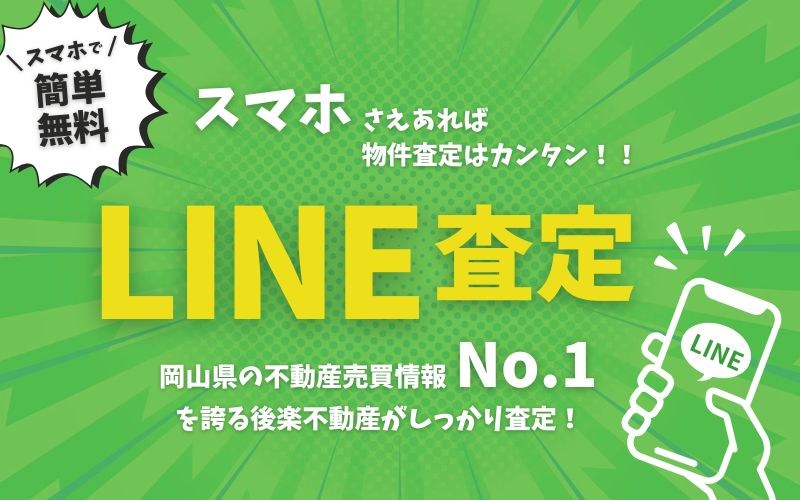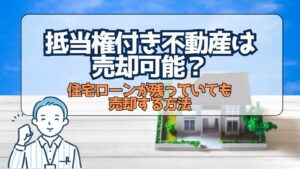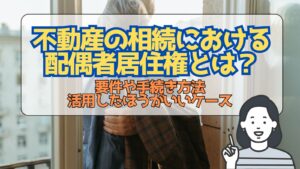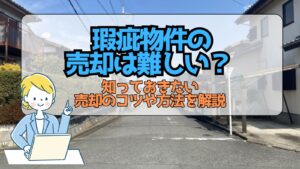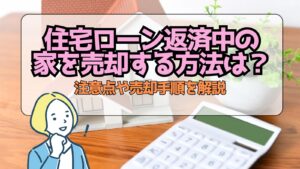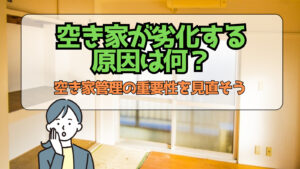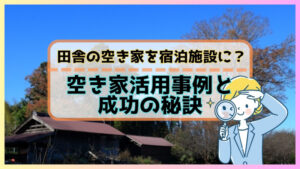共有名義不動産の売却方法を徹底解説|相続時の注意点とトラブル回避のポイント
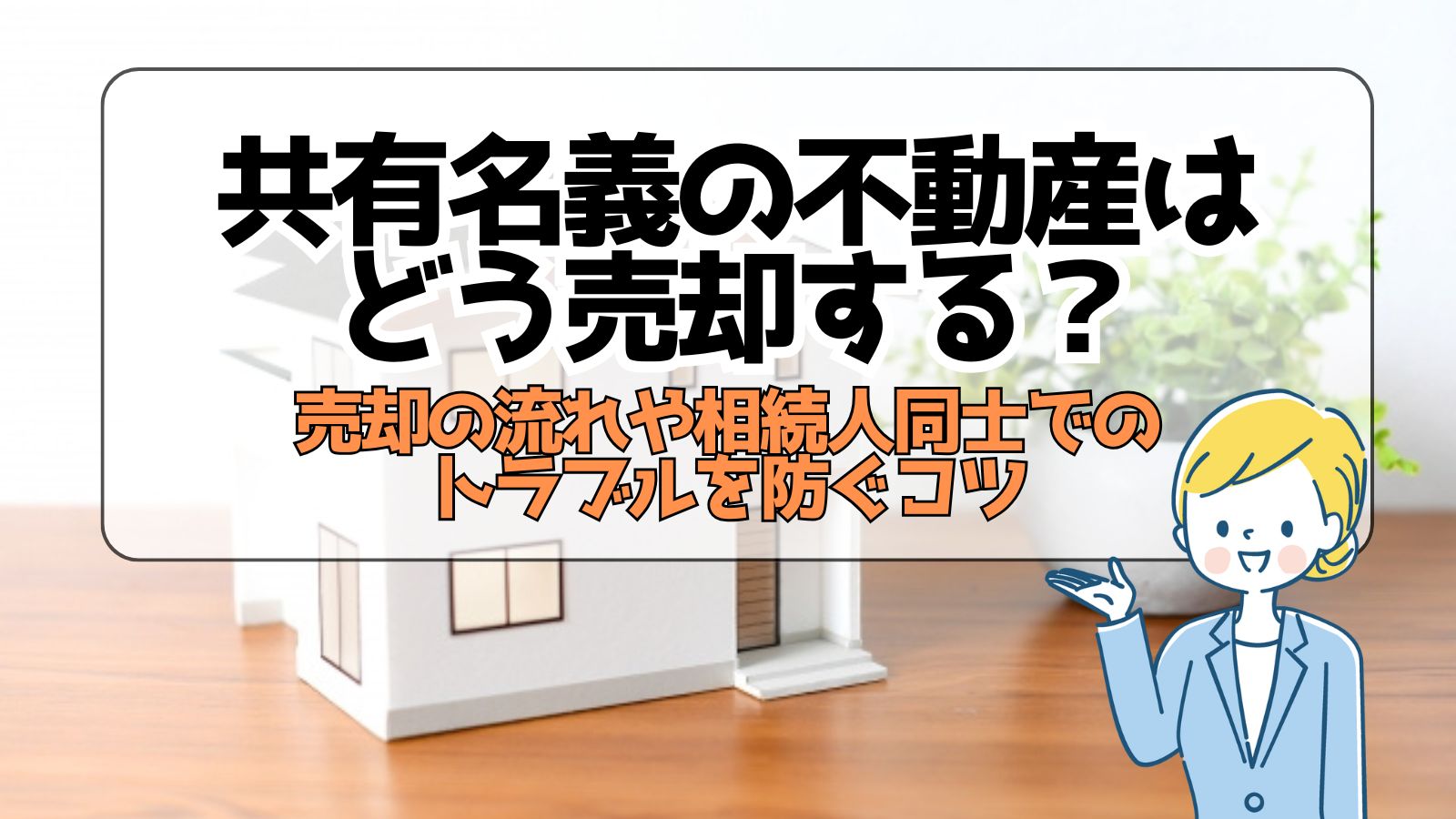
共有名義の不動産を売却するには、所有者全員の合意が必要です。そのため、単独名義の不動産に比べて手続きが複雑になりやすく、話し合いが進まずに売却が滞るケースも少なくありません。特に相続によって共有名義となった不動産では、相続人同士の意見の違いからトラブルに発展することもあります。
本記事では、共有名義不動産の基本から売却方法、手続きの流れ、トラブルを避けてスムーズに売却するためのポイントをわかりやすく解説します。
共有名義不動産とは?

共有名義不動産とは、1つの不動産を複数の人が共同で所有している状態を指し、共有不動産とも呼ばれます。主に相続や共同購入などが不動産が共有名義になる理由です。
共有名義不動産では共有者全員の権利が認められており、それぞれが持分(所有割合)を持っています。そのため、売却や賃貸などの利用に関しても、共有者全員の合意が欠かせません。
単独名義に比べると意思決定に時間がかかり、トラブルも起こりやすい状態です。
以下に、共有名義と単独名義の違いを表でまとめました。
| 項目 | 共有名義 | 単独名義 |
|---|---|---|
| 所有者の人数 | 複数人が不動産を共有 | 一人が所有 |
| 意思決定 | 全員の合意が必要 | 個人の判断で自由に決定可能 |
| 費用負担 | 費用を持分割合に応じて共有者間で分担 | 所有者が全額負担 |
| 所有権の範囲 | 不動産全体に対して持分を保有 | 不動産全体に対して完全な権利 |
| トラブル発生リスク | 意見対立や連絡不足などでトラブルが発生しやすい | トラブルのリスクは少ない |
| 売却時の手続き | 共有者全員の合意が必要 | 所有者の単独の意思で売却可能 |
| 資産の公平性 | 持分を割り当てることで公平性を確保できる | 公平性の議論が不要 |
| 名義変更の手続き | 持分譲渡などの複雑な手続きが必要 | 単純な変更手続きで完了 |
共有名義と単独名義にはそれぞれ特有のメリットとデメリットがあります。状況に応じて、適切に選択や対策を行いましょう。
共有名義不動産の特徴

共有名義不動産にはどのような特徴があるのか、以下に挙げていきます。
所有者が複数存在する
共有名義負動産には複数の所有者が存在するということは、大きな特徴です。共有名義不動産では、売却や賃貸など大きな決定をする際には、共有者全員の合意を得なくてはなりません。そのため、ひとたび意見が分かれてしまうと意思決定が進みにくく、売却などがスムーズにできなくなる恐れがあります。
固定資産税の支払い義務や維持管理の責任も、複数の所有者で分担されます。ただし、それぞれの権利を尊重する必要があるため、共有者間での調整が必要です。
持分割合が決まっている
共有名義の不動産において、各所有者が保有する権利や割合を「持分」と呼び、この割合に応じて売却の利益や負担が分配されます。持ち分は通常、共有者間で公平に配分されますが、相続や購入時の条件によって異なる場合もあります。
たとえ持分割合が小さくても、意思決定の際には関与しなくてはならず、全ての所有者が不動産全体についての権利を持っています。
相続人全員の合意なしに賃貸や売却ができない
共有名義では、全員が同意しなければ売却や賃貸などの重要な決定を行えません。共有者全員が不動産の利用や売却について、等しく権利を持っています。
全員の合意が必要とすることで、一部の共有者が勝手に意思決定を行うリスクが回避されます。一方で、意思決定に時間がかかったり意見の対立から感情的になったりして、話し合いが難航することもあります。
共有名義不動産を売却する方法

共有名義不動産を売却する際に、全員の合意を得て売却する以外にもいくつかの方法がありますのでご紹介します。それぞれのメリットとデメリットを考慮した上で、適切な売却方法を選択するとよいでしょう。
全員の合意を得て売却
共有名義不動産の売却で最も一般的な方法が、共有者全員が同意して売却手続きを進めることです。この方法では、共有者全員が売却の目的や条件に納得している状態を作り出すことが求められます。ただし、全員の合意を得るには話し合いや調整に時間がかかります。話し合いの結果合意が得られなければ、売却はできません。
合意形成のためには、共有者全員が参加できるコミュニケーションの場を設けることが大切です。例えば、定期的な会議やオンラインを活用することで、遠方に住んでいる共有者との連絡が途切れることを防ぎます。
自分の持分だけを売却
共有名義不動産では、自分の持分だけを第三者に売却することが法律上可能です。他の共有者の同意を得る必要はありません。ただし、買い手にとっては不動産全体の所有権を得られるわけではなく、自由に利用や処分ができないため、購入希望者を見つけるのは難しいのが実情です。
また、売却後に他の共有者との間でトラブルに発展するリスクもあるため、持分売却を検討する際は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
共有者間での持分売却(持分譲渡)
共有者間で持分を売却することもできます。これにより共有者の数が減り、話し合いなどの手間は簡素化されます。
共有者間での持分売却は、法律上、原則として他の共有者の同意を得る必要はありません。ただし、後々の関係悪化を防ぐためにも、売却前に他の共有者へ相談や報告をしておくことが望ましいでしょう。
共有名義の不動産を売却する際に必要な書類

共有名義不動産を売却する際には、以下の書類を準備しておく必要があります。
- 登記済権利証(もしくは登記識別情報)
- 固定資産税納税通知書
- 共有者全員の印鑑証明書
- 身分証明書(運転免許証など)
- 必要に応じて土地測量図や境界確認書(特に土地売却の場合)
物件の種類や状況によって、必要な書類は多少異なる場合があります。あらかじめこれらを揃えておくことで、売却手続きがスムーズに進められます。
共有名義不動産のメリットとデメリット

共有名義の不動産には、共有者間で費用や管理の負担を分担できるというメリットがある一方で、意思決定に時間がかかることやトラブルの発生リスクが伴うというデメリットもあります。本章では、共有不動産の具体的なメリットとデメリットを解説しています。
メリット
- 費用や手間を分担できる
- 不動産を公平に分配できる
固定資産税や維持費の負担を共有者で分けられるのは、共有不動産のメリットでしょう。例えば、一人で大きな不動産を管理する場合、税金や修繕にかかるコストが経済的なプレッシャーになることがありますが、共有名義であれば負担を均等に分けることで、コストを効率よく抑えることができます。
また、持分が各共有者に振り分けられると、相続時に公平性が保たれるという点もメリットと言えます。
デメリット
- 売却か活用の際には共有者全員の同意が必要
- 利益や負担の分配が複雑
- 相続時のトラブルの原因になる
共有者全員の同意がないと売却か賃貸ができないことは、デメリットです。また、共有者が多いと合意までに時間がかかることが多いのも、デメリットと感じる人は多いでしょう。
さらに、相続時のトラブルが起きやすくなってしまうのもデメリットです。例えば、親の介護や家の管理を行っていた相続人への分配が少ないと、自分の役割や貢献が十分に評価されていないと感じて不満が出やすくなります。
共有名義不動産を売却する場合の流れ

共有名義不動産を売却する際の流れは、次の6STEPを経て行われます。
①共有者をすべて確認する
まずは正しく共有者を把握しておくことが大切です。共有者を調べる確実な方法は、法務局で登記簿謄本を取得することです。
登記簿謄本には、共有者の氏名や持分割合が記載されているため、正確な情報を把握できます。相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は、郵便やメールを活用して正式な通知を行うことが効果的です。
②窓口担当になる人を決める
窓口担当になる人を決めておくと、売却がスムーズに進みます。窓口となる人は、売却する不動産の近くに住んでいる人やコミュニケーション能力が高い人、時間に余裕があり平日の昼間に活動できる人が望ましいでしょう。
忙しい共有者が担当者になると、手続きが遅れる可能性があります。その中でも共有者間で信頼を得ている人が担当すると、意思決定がスムーズに進むはずです。
③費用負担の割合を決める
次に、売却にかかるコストの分担方法を決めておきます。
- 不動産会社への仲介手数料
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 測量費や境界確定費用
- 解体費用(必要に応じて)
- 残置物撤去費用
不動産売却にはさまざまなコストが発生します。これらの負担割合をどのようにするのかを共有者の間で決めておかなくてはなりません。一般的には、持分割合を基準にして決定されることが多いでしょう。窓口担当者の労力を考慮し、費用の負担を調整することもあります。
売却後に得た利益からかかった費用を差し引く方法も有効です。この方法だと事前に手元資金を準備する必要がないため、負担が軽減されます。
いずれの方法にしても、共有者間で十分に話し合って決めることが重要です。
④最低売却価格を決める
最低売却価格とは、不動産を売却する際に、共有者全員が納得して設定する「これ以上低い価格では売却しない」という基準価格のことです。最低売却価格を決める際には、不動産会社へ査定を依頼し価格の目安としましょう。
過去のデータや市場動向をもとに、スムーズに売却できるであろう価格を提示してくれます。複数の不動産会社に査定の見積もりを依頼し、結果を比較検討することで、共有者全員が納得できる最低売却価格が決定するでしょう。
⑤売却活動を行う
最低売却価格が決定した後、不動産会社を活用して物件を市場に出します。不動産会社は買い手の募集を中心に担当し、広告活動や顧客への情報提供を行います。
一方、窓口担当者は不動産会社と連携しながら必要に応じて物件の内覧対応や、購入希望者との価格交渉を行います。また、共有者の意向を反映させるため、担当者は共有者間で合意した条件を買い手に伝える重要な役割を果たします。
⑥売却後に確定申告を行う
売却が無事に完了し利益が出た場合は、確定申告を忘れずに行います。不動産を売却して利益(譲渡益)が発生した場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。
確定申告ではこの譲渡益を正確に計算し、税務署への申告が必要です。特定の条件を満たす場合、譲渡所得に対して「居住用財産の特別控除」や「買換特例」などが適用されることがあります。
これらの控除を適切に活用するためにも、確定申告が必要です。
共有名義不動産で相続人間のトラブルを回避するには?

共有名義不動産で相続人間のトラブルを回避するには、どのようなところに気を付ければいいのでしょうか。
- 事前によく話し合いを行う
- 共有名義の解消も検討する
- 裁判所での手続きについて知っておく
- 専門家にアドバイスを求める
相続人同士のコミュニケーションが取れていないと、誤解が生まれて合意形成に影響します。事前の話し合いを十分に行うことで誤解を防ぎ、スムーズな売却へとつながります。
特定の共有者に買い取ってもらうことで、共有名義を解消することも検討してみてもよいでしょう。共有名義不動産を無断で売却された場合などは、法的手続きを取ることも考えなくてはなりません。
お金の問題については弁護士や税理士へ、不動産売却については不動産会社へ、わからないことや困ったことがあれば遠慮なく相談してみるとよいでしょう。
まとめ
本記事では、共有名義不動産の特徴や売却方法、売却までの流れ、さらに相続人同士でのトラブルを回避するためのポイントについて詳しく解説しました。特に、共有者全員の合意形成や窓口担当者の選定、費用分担の決定は、売却を成功させるために欠かせない要素です。
共有名義の不動産を売却する際は、十分な話し合いと準備を行い、専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。
後楽不動産では、共有名義の売却に関するご相談も丁寧にサポートしております。
「どう進めればいいかわからない」「トラブルを防ぎたい」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。