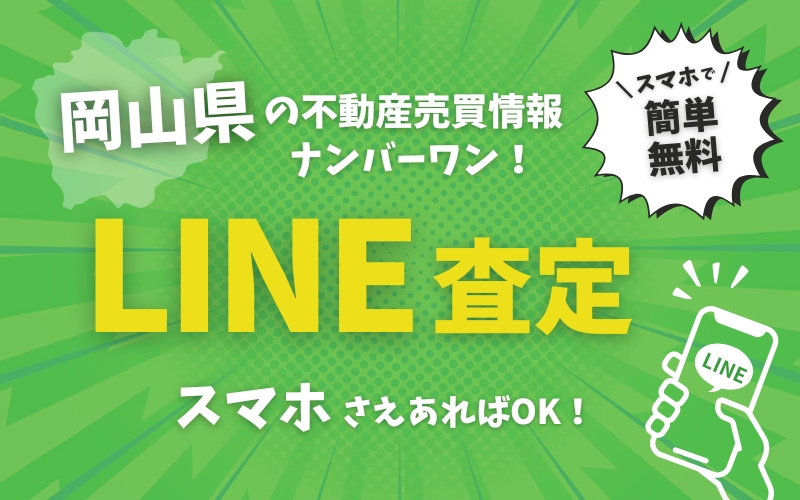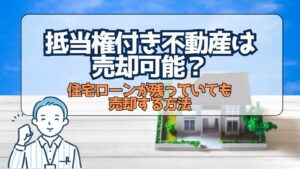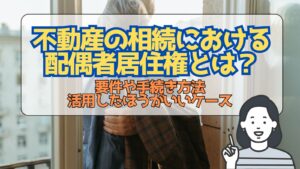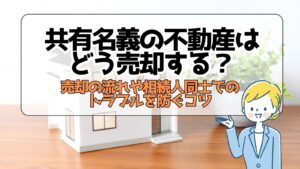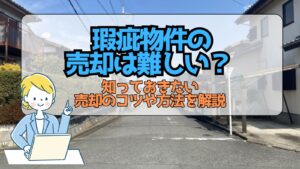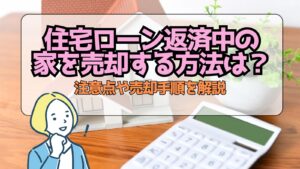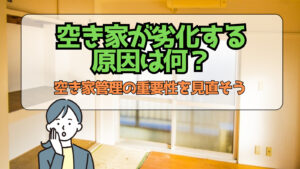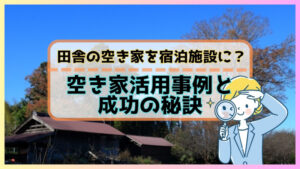【空き家が資産から負債に】なぜ劣化が加速する?放置リスクと今すぐ始めるべき基本管理

空き家を所有している方にとって、「とりあえず置いてあるだけだから大丈夫」という考えは非常に危険です。人が住んでいないことそのものが、建物の劣化を加速させる最大の原因になるからです。日々の換気や通水といった人の手によるケアがなくなると、湿気やカビ、構造の傷みが急速に進みます。
空き家は、放っておけば大切な資産から「負担」へと変わり、最終的には「特定空家」指定による税負担の増加や売却困難化といった深刻なリスクを招きます。
この記事では、空き家が劣化する具体的な原因から、放置リスク、基本管理の方法、そして売却や管理代行といった現実的な解決策までを解説します。大切な資産を守るため、「今」どう向き合うべきか、この記事でご確認ください。
どうして空き家は劣化するの?人が住まないことによる4つの深刻な影響

一見すると「ただ人がいないだけ」と思われがちな空き家ですが、実は“人が住んでいないこと”そのものが建物の劣化を加速させる大きな要因になります。住宅は、日々の換気や通水、清掃といった人の手による「当たり前の行動」によって健康を保たれている、いわば“生きた器”のような存在だからです。
これらのケアがなくなると、建物の健康状態は一気に悪化し、老朽化のスピードを速めてしまいます。以下では、空き家で特に注意すべき代表的な4つの深刻な劣化要因について詳しく見ていきましょう。
換気不足による湿気・カビ・腐食
空き家の劣化の中でも、最も基本的でありながら深刻なのが「換気不足」です。人が住んでいない家は、窓もドアも長期間閉め切られ、空気の入れ替えがまったく行われません。この状態が続くと、室内に湿気が溜まり、カビや腐食が発生しやすくなります。特に梅雨や夏場など湿度が高い季節は、その影響が一気に加速します。
湿気は畳や壁紙を傷めるだけでなく、木材部分が膨張したり腐ったりし、家の構造そのものがダメージを受けることもあります。気づいたときには大掛かりな修繕が必要になるケースも少なくありません。
雨漏りによる構造損傷と発見の遅れ
空き家のもう一つの大きなリスクは、知らぬ間に進行する「雨漏り」です。定期的に住まわれている家であれば、小さな雨漏りにもすぐに気づけます。しかし、空き家の場合はチェックが遅れ、屋根や外壁の小さなひび割れやコーキングの劣化などからじわじわと雨水が侵入しやすくなります。
一度水が入り込むと、木材の腐食や鉄骨のサビといった深刻な構造ダメージへと発展する可能性が高まります。特に天井裏や壁の内部に水が回ると、表面からは見えにくいため、気づいた頃にはすでに家の強度が大きく損なわれていることもあります。
配管の錆や詰まり、ガス管の劣化
空き家では「水を使わないこと」自体が、設備の劣化を引き起こす要因になります。水もガスも使われないまま放置されると、配管の中で「水の循環」が止まり、さまざまな不具合が起きやすくなります。例えば、給排水管では内部に水垢や汚れが沈着しやすくなり、腐食や詰まりの原因に。錆びが進行すると、再び水を通したときに赤水が出たり、最悪の場合、配管が破裂してしまうこともあります。
また、ガス管も長期間使わないと劣化し、再利用時にガス漏れや破裂といった危険な事態を引き起こす可能性があります。特に古い住宅では、設備の老朽化が早く進むため、注意が必要です。
害虫・害獣の侵入と衛生問題
空き家は、人の出入りがないことで害虫や害獣にとって格好の住処になります。特にゴキブリやシロアリは、空き家の静かな環境を好み、床下や壁の内部に巣を作ることがあります。シロアリが発生すると、家の柱や床を内部から食い荒らし、建物の耐久性そのものを損なう恐れがあります。また、ネズミやハクビシンなどの害獣が侵入すると、天井裏や床下で巣を作り、断熱材を引きちぎったり、電気配線をかじることで火災の原因になることも。さらに、糞尿による悪臭や衛生面の悪化も深刻な問題となります。
空き家を放置することで生じる具体的な3大リスク

空き家の劣化は、単なる見た目の問題にとどまりません。放置し続ければ、いずれ所有者にとって深刻な経済的負担や法的責任へと発展していきます。このセクションでは、空き家を長期間放置することで起こり得る主なリスクを、「経済的損失」「法的リスク」「地域社会への影響」といった観点から具体的に解説します。
リスク1:資産価値の低下と売却の困難化(経済的損失)
劣化が進んだ空き家は、どうしても買い手に敬遠されがちです。屋根の破損や壁紙の剥がれ、床の腐食といった見た目の劣化だけでなく、配管・電気系統などの内部設備の不具合も、購入希望者にとっては大きな不安要素になります。「この家を直すのに、どれくらいお金がかかるのか?」という懸念から、購入をためらわれるケースが多く、結果として売却までに時間がかかり、相場より大幅に値下げしないと売れないという状況に陥りやすくなります。
また、「いつか貸そう」と考えていた空き家も、長期間放置されたままだと、内装・水回り・配管など広範囲にわたる改修工事が必要になり、賃貸への転用に高額な修繕コストが発生し、投資としての収益性が悪化する現実もあります。空き家は、「時間が経つほど売りづらくなる資産」なのです。
リスク2:「特定空家」に指定される法的リスクと税負担の激増
空き家の劣化が進み、倒壊の危険性や衛生環境の悪化が顕著になると、自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。これは、周辺住民の安全や景観を守るために、行政が改善命令や指導を行う制度です。
特定空家に指定されると、最も大きな影響として、住宅用地の固定資産税軽減(最大6分の1)が打ち切られ、税負担が大幅に増えることになります。さらに、改善命令に従わない場合は、過料(罰金)や行政代執行(強制解体)の対象になり、解体や修繕の費用はすべて所有者負担となります。「誰にも迷惑をかけていないから…」と思っていても、ある日突然、多額の出費が一気に降りかかるリスクを抱えることになります。
【関連記事】空き家を放置すると危険!「特定空き家」に指定されるリスクとその対策-【岡山県】不動産売却・査定・買取|後楽不動産の安心サポート
リスク3:地域社会への悪影響と近隣トラブル
空き家の外観が荒れてくると、その影響は周囲の住環境にもじわじわと波及していきます。たとえば、庭の雑草が伸び放題になり景観を損なったり、害虫や動物が発生し近隣の家にまで被害が及んだりします。
こうした状態が続けば、「あの家なんとかして」と近隣からのクレームや苦情に発展することも珍しくありません。最初は小さなことでも、放置することで「近所付き合いの悪化」や「地域からの孤立」といった深刻なトラブルに発展する恐れがあります。空き家は、所有者だけでなく地域にも影響を与える存在だという認識が大切です。
空き家の劣化を防ぐためにやるべき3つの基本管理

空き家の劣化を防ぐために、特別な知識や高額な設備投資が必要なわけではありません。大切なのは「人が住んでいる状態に少しでも近づけること」です。つまり、日常的に行われていた“当たり前の行動”を定期的に再現することが、劣化を最小限に抑える第一歩となります。
ここでは、今すぐ誰でも取り組める基本的な管理方法を3つに絞って紹介します。
管理①:月1回の「換気と通水」作業の習慣化
空き家の劣化を防ぐうえで最もシンプルかつ効果的なのが「空気と水を流す」ことです。月1回の実施を習慣化しましょう。
湿気を逃がすことで、カビや木材の腐食、内装材の劣化を大幅に防げます。換気の際は、月に1度はすべての窓・ドアを開けて風を通し、押入れや収納の扉も開けて空気をこもらせないようにしてください。雨の翌日など湿度が高い日は避け、晴れた日に実施するのがポイントです。
通水は、キッチン・洗面台・浴室・トイレなどすべての蛇口を開け、1〜2分水を流すのが基本です。配管内の錆、詰まり、悪臭の予防に効果があり、給排水管やトラップ内の水が乾ききるのを防ぎ、悪臭や虫の侵入も抑えられます。
管理②:清掃と簡易メンテナンス(外構含む)
空き家でも“人の気配”を保つことが重要です。そのためには、室内外の清掃と最低限のメンテナンスを定期的に行うことが求められます。
室内の清掃は、ホコリ取りや床の掃除機がけ、キッチンや浴室のカビチェックと簡易拭き掃除を行い、不用品やゴミの処分で害虫の温床をなくします。
外構メンテナンスでは、雑草の除去(特に道路側・隣家との境界部)や、郵便物の整理が大切です。郵便物が溜まっていると「空き家」と分かりやすくなり、不審者の標的になるリスクも高まります。見た目の美しさは、劣化防止だけでなく「近隣との良好な関係維持」にも直結します。
管理③:害虫・害獣対策と侵入経路の封鎖
空き家では害虫や害獣の侵入リスクが高まるため、予防措置をしっかり講じることが重要です。ネズミ用忌避剤や超音波発生器の設置、シロアリ対策として床下の点検など、具体的な予防策を取りましょう。特に重要なのが侵入経路の封鎖です。虫の侵入を防ぐため、排水口にフタをしたり、網戸の破れをチェックしたりしましょう。また、換気口・床下通気口に金網を設置すれば、大型の害獣の侵入を効果的にブロックできます。
「管理が難しい」と感じたときの3つの現実的な選択肢

ここまで紹介したように、空き家を劣化させないためには、定期的な換気・通水・清掃・点検が欠かせません。しかし、「遠方に住んでいて行けない」「高齢で体力的に難しい」「仕事や子育てで時間が取れない」といった理由で、思うように管理できない人も多いのが現実です。
そんなときは、“自分ひとりですべて管理しなければならない”という思い込みをいったん手放し、状況に応じた現実的な選択肢を考えてみましょう。
選択肢1:管理代行サービスや地元業者に一部を委託する
管理が難しい場合、まず検討したいのが「信頼できる第三者に任せる」方法です。最近では空き家の管理代行サービスが全国的に増えており、月に1回の換気・通水・清掃を定期的に行ってくれるプランなども用意されています。
主な委託内容には、建物内の換気・通水・簡易清掃に加え、建物外の草刈りや郵便物の整理、そして定期巡回と報告レポート(写真付き)の提出が含まれます。費用はかかりますが、手間と劣化リスクを大幅に削減できるのが大きなメリットです。地元の工務店や不動産会社が提供していることも多いため、まずはエリア内で実績がある業者を探して相談してみるのがおすすめです。
選択肢2:「売却」で資産を整理し、負担から解放される
「今後使う予定がない」「管理の手間や費用に限界を感じている」そんなときは、“空き家を売る”という選択肢を前向きに検討してみてください。売却によって得られる最大のメリットは、固定資産税や維持費の負担から完全に解放されることです。これにより、相続時の“負動産”リスクを未然に防ぎ、まとまった資金を別の目的に活用できます。
売却には、希望価格に近い金額で売れる可能性のある一般仲介売却、スピード重視で現況のまま買い取ってもらえる不動産会社による買取、築古物件でも再生目的で購入してくれるリノベーション会社への売却など、複数のルートがあり、自分の状況や希望に合った方法を選ぶことができます。「空き家を売ること=諦めること」ではなく、“資産の持ち方を見直す”という前向きなステップです。
選択肢3:賃貸・その他の活用も視野に入れる
「まだ住める家なのに、ただ手放すのはもったいない」と感じている方には、賃貸運用や活用型の利活用も有力な選択肢になります。空き家に“人の気配”を取り戻すことで、劣化防止と収益化の両立が期待できます。
主な活用パターンとしては、家賃収入を得ながら傷みを防げる賃貸住宅、観光客向けの高収益も期待できる民泊施設(Airbnbなど)、または改装せずに運用できるケースもあるレンタルスペースやコワーキングスペースなどがあります。収益化と劣化防止を両立できるメリットは大きいですが、初期投資や管理体制の構築、入居者・利用者の確保といったリスクも伴うため、市場ニーズをしっかり見極めることが重要です。
空き家対策を「売却」「賃貸」「その他の方法」の大きく3つに分けて解説▼
【関連記事】【空き家対策完全ガイド】空き家の問題を解決する具体的な方法を解説-【岡山県】不動産売却・査定・買取|後楽不動産の安心サポート
まとめ:空き家管理は「資産を守る」という意識から始めよう
空き家を放置することは、資産を「負担」に変える最大のリスクです。湿気や害獣による建物の劣化が進むだけでなく、「特定空家」指定による税負担の激増や近隣トラブルに直結します。
空き家管理は「資産を守る」意識から始め、放置しないことが最大のリスクヘッジです。完璧でなくていいので、「換気と通水」といった基本管理を定期的に行いましょう。もし、管理が難しいと感じたら、一人で悩まず、売却や管理代行といった現実的な解決策を検討すべきです。
まずは、専門家である不動産会社に相談し、ご自身の空き家にとって最適な方法を見つけることから始めてください。今日できる小さな行動が、将来の大きな後悔を防ぎます。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る