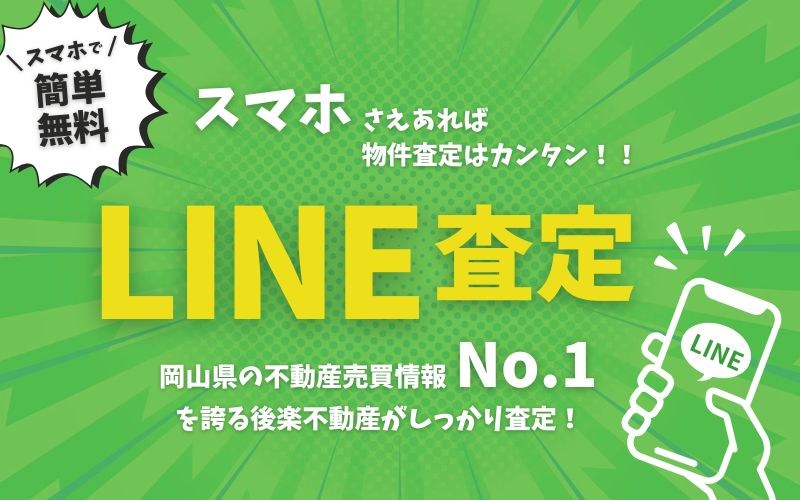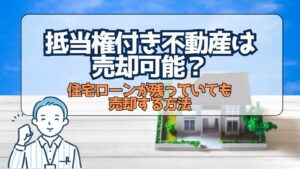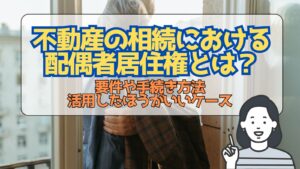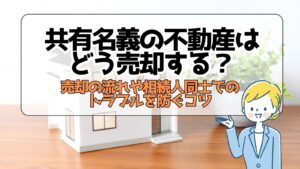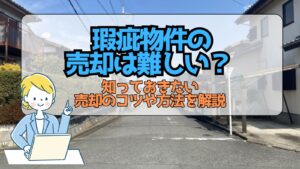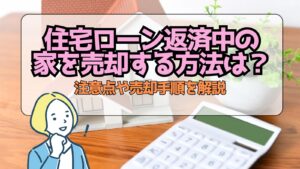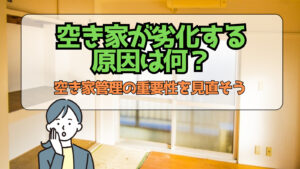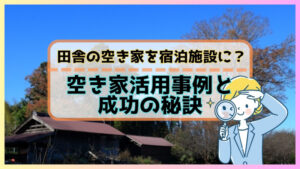【リフォーム?解体?】老朽化した空き家、後回しにする前に考えたい対策
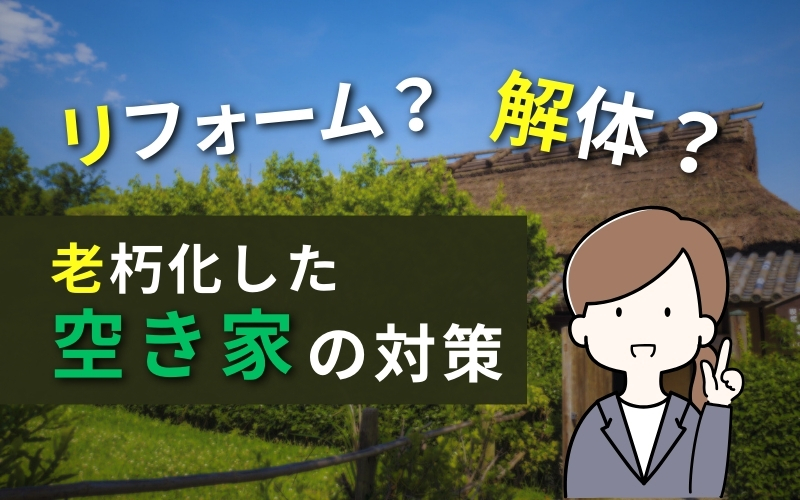
使わないまま、手をつけられずに年月だけが過ぎていく空き家。
「管理が大変」「まとまったお金がない」「今は忙しいから…」――
そんな理由で放置していると、気づかぬうちに大きな損失やトラブルを招くリスクがあります。
建物の老朽化、不法侵入、害虫の発生、近隣からの苦情、税制上の不利益…。
空き家を放置することは、ただの“先延ばし”では済まされない問題です。
けれど同時に、空き家には可能性もあります。
正しく手を打てば、地域の資産として再生させることも、収益を生む存在に変えることもできるのです。
この記事では、「空き家をどうすべきか悩んでいる方」に向けて、
放置によるリスクと、リフォーム・解体という2つの解決策、そして判断のポイントを丁寧に解説します。
まずは現状を正しく知ることから、未来の選択が始まります。
この記事を監修した人

岩冨 良二
後楽不動産 売買事業部 係長
不動産業界歴26年のベテランで、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格を持つエキスパート。豊富な知識と実績でお客様から厚い信頼を得ており、売買事業部のエースとして活躍中。複雑な取引もスムーズにサポートし、最適な提案を行う頼れるプロフェッショナルでありながら、社内のムードメーカーとしても周囲を明るくする存在。
放置された空き家がもたらす“見えないリスク”

「空き家は、誰も住んでいないだけでしょ?」
そう思って放置していると、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
空き家を長期間放置すると、以下のようなリスクが現実のものになります。
建物の倒壊リスク
誰も住んでいない家は湿気や温度変化にさらされ、劣化スピードが驚くほど早まります。
屋根の崩落、外壁の剥がれ、床の腐食などが進行すると、近隣に被害を及ぼす倒壊の危険性すらあります。
害虫・害獣の発生
換気されない空間には湿気がこもり、ゴキブリやネズミ、シロアリなどの温床に。
一度繁殖してしまえば、近隣の住宅にまで被害が広がることも。近所とのトラブルの原因になります。
不法侵入・放火などの犯罪リスク
「誰も見ていない」空き家は、不法侵入者や不審者にとって絶好の標的。
実際に、放火や不法投棄、盗難などの事件が起きた事例も多数報告されています。
近隣住民からの苦情や訴訟リスク
見た目が荒れてくると、「地域の景観を損ねる」「草木が越境してきた」など、近隣からの苦情が増加します。
場合によっては、管理不全が原因で民事トラブルに発展することもあります。
税金の優遇が打ち切られる可能性
通常、住宅が建っている土地には固定資産税の優遇措置がありますが、
建物が“特定空家”に指定されると、この軽減措置が解除され、課税額が数倍になるケースもあります。
「特定空家」に指定されると、どうなるか?

平成26年に施行された「空家等対策特別措置法」では、適切に管理されていない空き家を“特定空家”に指定できる仕組みが導入されています。
特定空家の指定基準(一例)
- 倒壊の危険がある
- ごみの放置などで著しく不衛生
- 景観を著しく損なっている
- 防犯上、著しい問題がある
一度“特定空家”に指定されると、自治体から改善の勧告・命令を受け、期限内に改善しない場合は罰金や行政代執行(強制解体)の対象になります。しかもその費用は、最終的に所有者に請求される可能性も。

「リフォーム」or「解体」今すぐ検討すべき2つの選択肢

空き家は、「放置しておけばいつか自然に解決する」ような問題ではありません。
老朽化やトラブルが進行する前に、早急な対策が求められます。
空き家対策には大きく分けて、次の2つの方向性があります。
【選択肢①】空き家をリフォームして再活用|収益化・資産価値アップに
建物の状態がまだ良好であれば、リフォームによって空き家に新たな命を吹き込むことができます。居住用に限らず、賃貸住宅や民泊施設、地域の拠点など、多様な形での再活用が可能になるのが大きな魅力です。
リフォームの主なメリット
- 賃貸住宅や民泊施設として活用し、安定した収入を得られる
- セカンドハウスや二世帯住宅として、家族のライフスタイルに合わせて再利用できる
- 将来的に売却する際に、資産価値の向上が期待できる
- 外観や住環境が整い、地域の景観改善にもつながる
注意したいデメリット・課題点
- 初期費用が比較的高額(数百万円単位)になりやすい
- 築年数や構造によっては、耐震補強や配管更新など追加費用が発生する可能性がある
- リフォーム後も、定期的な換気・清掃・点検などの維持管理が欠かせない
- 立地条件や地域ニーズによっては、活用後も思うような収益につながらない場合がある
リフォームは「手をかければ価値が高まる」一方で、費用対効果や将来の活用イメージを冷静に見極めることが大切です。また、直したら終わりではなく、長期的な管理を前提とした計画を立てることが成功のカギとなります。
【選択肢②】空き家を解体して土地活用|将来性の高い資産へと転換
老朽化が進み、安全性や再利用の見込みが低い場合は、思い切って建物を解体し、更地にするという選択も有効です。倒壊リスクや管理負担から解放されるだけでなく、土地としての新たな活用や売却といった可能性が広がります。
解体の主なメリット
- 老朽化による倒壊リスクや、草木の繁茂といった管理の手間から解放される
- 更地にすることで、駐車場・家庭菜園・太陽光設置・小規模店舗用地など、多目的な活用が可能に
- 土地の売却がしやすくなり、現金化までの期間を短縮できる
- 空き家による景観悪化や近隣トラブルを未然に防ぎ、防犯面でも安心感が増す
また、多くの自治体では空き家の解体費用に対する補助金制度を設けています。補助の有無や条件は地域ごとに異なるため、市区町村のホームページや窓口での事前確認をおすすめします。
注意したいデメリット・課題点
- 解体工事には100〜200万円程度の費用がかかり、リフォームよりは安価でも出費は避けられない
- 更地にすると、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1軽減)が適用されなくなり、税額が増加する可能性がある
- 活用目的が決まっていないまま解体すると、土地が長期間放置されるリスクも
- 地中埋設物や隣地との境界問題など、解体後に予想外の課題が発生することもある
解体は、空き家の問題を根本から解消できる実行力のある選択肢です。ただし、費用・税制・今後の土地活用まで見据えたうえでの判断が重要となります。
「解体して終わり」ではなく、その先の活用・管理まで視野に入れて検討しましょう。

空き家はリフォームか解体か?迷ったときに見るべき3つの判断基準

「リフォームして再活用すべきか、それとも思い切って解体すべきか…」
多くの空き家所有者がぶつかる悩みです。
結論から言えば、状況や目的に応じた判断が必要です。
以下の3つの視点から冷静に検討してみましょう。
1. 建物の状態|再生可能かどうかを冷静に見極める
まず最初に確認すべきは、建物そのものが「安全に使える状態かどうか」です。老朽化が進んだ空き家は見た目では判断しにくいため、専門的な視点からのチェックが不可欠です。
主なチェックポイント
- 屋根や外壁に大きな劣化や破損がないか(雨漏り・剥がれなど)
- 床下や柱に腐食やシロアリ被害が見られないか
- 基礎部分にひび割れや傾きが生じていないか
- 耐震性が確保されているか(特に1981年以前に建てられた木造住宅は注意)
特に空き家の場合、長期間の放置によって見えない部分が劣化していることも多いため、専門家による「建物診断(インスペクション)」を受けることを強くおすすめします。診断結果をもとに、リフォームが可能か、あるいは解体して建て替え・土地活用へと進むべきかを冷静に判断できます。
判断の目安
- 修繕費用が高額になりそうな場合
- 構造上の安全性に不安がある場合
- 再利用の用途が決まっていない場合
これらに当てはまる場合は、無理にリフォームを選ぶよりも、解体を前提とした新たな活用を検討した方が、将来的なリスクを抑えられるケースが多いです。
2. 活用目的|その空き家を「どう使いたいか」を明確に
空き家をどうするかを判断するうえで、まず明確にしたいのが「今後どのように活用したいか」という目的です。活用の方向性が決まっていれば、リフォームの内容や解体後の土地利用プランも、自然と導き出しやすくなります。
主な活用パターンとそれぞれの特徴
- 自分で住む予定がある
将来的に移住やUターンを考えている場合は、居住性や断熱・耐震といった機能面を重視したリフォームが必要です。 - 子世代や親族への引き継ぎを検討している
継承予定者の希望やライフスタイルに合わせて、将来の使いやすさ・安全性を見越した改修がポイントになります。 - 賃貸住宅や民泊などで収益化を目指す
間取りや設備を入居者ニーズに合う形に整えたり、宿泊施設としての法規制を満たす必要があります。エリアによっては空室リスクや競合状況も要チェックです。 - 売却を視野に入れている
最低限のリフォームで見た目を整えるだけでも売却価格や売れやすさが向上する可能性があります。一方で、状態が悪い場合は更地にして売った方が早く買い手がつくことも。
目的がはっきりしていれば、「どこまで手を入れるべきか」「どれくらい予算をかけるべきか」といった判断がブレにくくなります。反対に、「活用のイメージが湧かない」「使う予定がない」という場合は、更地にして資産価値を保ちつつ、将来的な柔軟な活用につなげるという選択も現実的です。
3. コストとリターンのバランス|数字で冷静に比較を
空き家の活用には、「リフォーム」でも「解体」でもある程度の初期費用が発生します。まずは、それぞれにどのくらいの費用がかかり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを把握しましょう。
| 項目 | 費用目安(一般例) | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|---|
| リフォーム ※設備交換と軽微な間取り変更程度 | 約400~800万円 | 建物の再活用が可能/収益化につながる | 状態によっては修繕費がかさむ場合も |
| 解体 ※一般的な戸建の解体費用 | 約100~300万円 | 管理負担がゼロに/土地売却がしやすい | 更地になると固定資産税が上がる可能性あり |
ただし、単に「金額が安い方を選ぶ」という判断はおすすめできません。
費用対効果だけでなく、以下のような視点も含めて総合的に検討することが重要です。
検討すべき追加ポイント
- 投資回収までにどれくらいの時間がかかるか(収益化や売却までの見込み)
- 地域の不動産ニーズ(賃貸需要があるエリアか/売却しやすい立地か)
- 自身または家族のライフプランとの整合性(将来住む予定があるか 等)
また、リフォームを検討する場合は、目的に合わせた計画的な内容にすることが非常に重要です。
- 売却を目的とするなら: ニーズに沿った最低限の改修で、見た目や使いやすさを整えるだけでも資産価値が上がるケースがあります。一方で、買い手の希望と合わない過剰リフォームは、かえって売りにくくなることも。
- 賃貸活用を目指すなら: ターゲット層(ファミリー・単身者・高齢者など)に合った間取りや設備でないと、空室リスクが高まります。特に地域性によってニーズは異なるため、不動産会社や管理会社と相談して相場を把握しておくことが大切です。
費用は「かけること」よりも「どう回収できるか」が鍵です。その空き家にどんな価値を生み出せるか、どれくらいの期間で効果を得られるかまで考えたうえで、リフォームか解体かを冷静に判断しましょう。
迷ったら、まずは「診断」と「相談」から
空き家をどうするか――
リフォームして再活用するか、思い切って解体し土地を活用するか。
どちらにもメリットと課題があり、正解は一つではありません。
重要なのは、
「その空き家をどう活かしたいのか」という目的を明確にし、
「建物の状態」「かかる費用」「将来のリターン」を総合的に見極めることです。
- 使える建物で、目的がはっきりしている → リフォームで価値を高める道
- 老朽化が進み、活用の見通しが立たない → 解体して柔軟な土地活用へ
どちらの選択をするにしても、感情や思い出だけでは判断しきれない場面が多いのも現実です。
だからこそ、まずはプロによる「建物診断」や、信頼できる地元の不動産会社への相談から始めてみてください。
空き家は、放置すればリスクになりますが、正しく向き合えば「地域に貢献できる資産」にもなります。
「このままでいいのかな」と感じたそのときが、動き出すタイミングです。
空き家の活用については以下の記事も参考になります▼