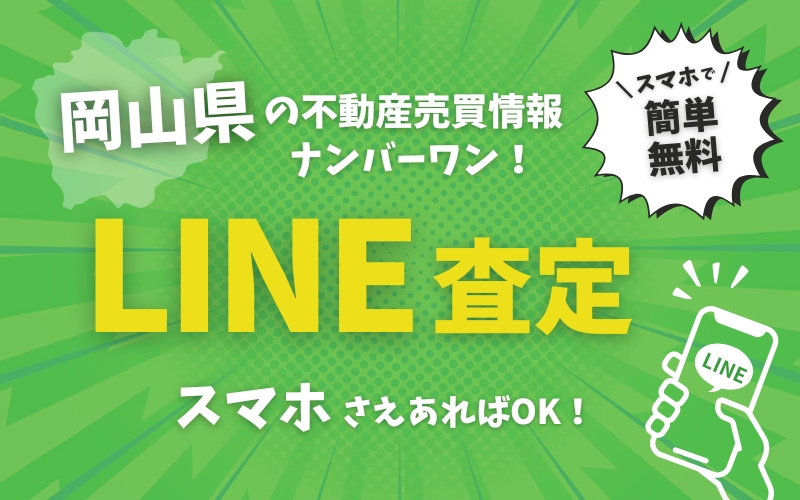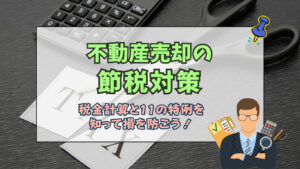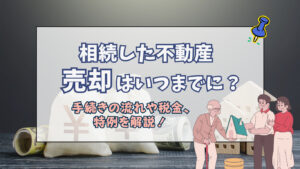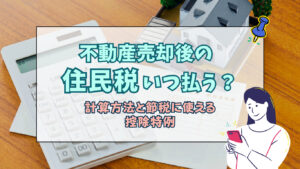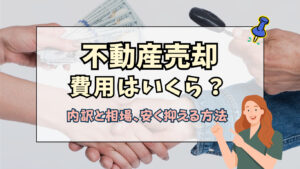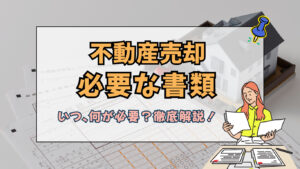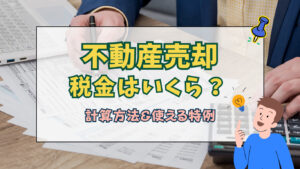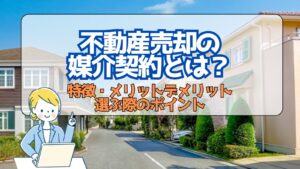不動産売却後の確定申告は必要?手続きのやり方や節税方法を分かりやすく解説

不動産という大きな資産を売却した後、「確定申告」という言葉に不安を感じていませんか。特に初めての経験だと、何から手をつければ良いのか、そもそも自分に手続きが必要なのかさえ分からず、戸惑うことも多いでしょう。
しかし、ご安心ください。不動産売却後の確定申告は、ポイントさえ押さえれば決して難しいものではありません。この記事では、確定申告が必要になるケースから、税金の計算方法、損をしないための節税制度、そして具体的な手続きの流れまで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る
不動産売却後の確定申告はどんな時に必要?

不動産を売却したからといって、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。まずは、ご自身の状況が確定申告を必要とするのか、それとも不要なのかを正しく理解することから始めましょう。申告が必要なのに放置してしまうと、後からペナルティが課される可能性もあるため、最初のこのステップが非常に重要です。
利益(譲渡所得)が出た場合は確定申告が必要
不動産を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として所得税と住民税の課税対象となるため、原則として確定申告が必要です。
譲渡所得とは、簡単に言うと「不動産を売却して得た儲け」のことです。具体的には、売却した金額そのものではなく、売却価格からその不動産を購入したときにかかった費用(取得費)や、売却するために直接かかった経費(譲渡費用)を差し引いた金額を指します。この計算の結果、1円でもプラスになれば申告義務が発生します。
参考:不動産等を売却した方へ|令和6年分確定申告特集
参考:No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁
| 売却の結果 | 確定申告の要否 | 理由 |
| 利益(譲渡所得)が出た | 必要 | 譲渡所得は所得税・住民税の課税対象であるため。 |
| 損失(譲渡損失)が出た | 原則不要 | 課税される所得がないため。ただし、特例を使う場合は必要。 |
損失が出た場合は原則不要だが申告した方がお得なことも
一方で、不動産を売却して損失が出た(譲渡損失)、つまり「購入した時よりも安く売れてしまった」場合は、課税される利益がないため確定申告は原則として不要です。しかし、ここで注意したいのが、たとえ損失が出た場合でも、確定申告をした方が税金面で有利になるケースがある点です。
マイホーム(居住用財産)の売却で出た損失は、給与所得など他の所得と相殺(損益通算)して所得税を減らしたり、翌年以降に損失を繰り越して税負担を軽減したりできる特例制度があります。これらの特例を利用するためには、損失が出ていても確定申告を行う必要があります。
参考:No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合|国税庁
参考:No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
確定申告をしなかった場合のペナルティ
もし確定申告が必要であるにもかかわらず、期限内に行わなかった場合、いくつかのペナルティが課される可能性があります。代表的なものに「無申告加算税」と「延滞税」があります。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して課されるもので、税務署の調査を受ける前に自主的に申告したか、調査後に申告したかで税率が変わります。延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息のように課される税金です。
本来納めるべき税金に加えて、これらの追徴課税を支払うことにならないよう、申告が必要な場合は必ず期限内に手続きを完了させましょう。
参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
参考:延滞税の計算方法|国税庁
確定申告の基本!譲渡所得と税金の計算方法

確定申告が必要だと分かったら、次に気になるのは「一体いくら税金を納めるのか」という点でしょう。不動産売却の税額は、譲渡所得を正確に計算することから始まります。
ここでは、その計算方法と、税額を左右する重要な要素である「取得費」「譲渡費用」、そして「所有期間」について詳しく見ていきましょう。
譲渡所得の計算式を理解する
譲渡所得は、以下の計算式で算出します。この式が全ての基本となります。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
例えば、5,000万円で売却したマンションの購入費用(取得費)が4,000万円、売却時の経費(譲渡費用)が200万円だった場合、譲渡所得は「5,000万円 – (4,000万円 + 200万円) = 800万円」となります。
ただし、マイホームの売却では3,000万円の特別控除が適用される場合があるため、その際は「800万円 – 3,000万円 = 0円(マイナスの場合は0円)」となり、課税対象となる譲渡所得は発生しません。
参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
参考:No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁
| 項目 | 内容 |
| 売却価格 | 不動産を売って買主から実際に受け取った金額。 |
| 取得費 | 売却した不動産を購入したときの代金や手数料など。 |
| 譲渡費用 | 売却するために直接かかった仲介手数料などの経費。 |
取得費に含められる費用
取得費は、単に不動産の購入代金だけではありません。購入時に支払った仲介手数料や、登記費用、不動産取得税、印紙税なども含まれます。また、増改築やリフォームにかかった費用も取得費に加えることができます。
これらの費用を証明する契約書や領収書は非常に重要ですので、大切に保管しておきましょう。建物については、所有期間中の減価償却費相当額を購入代金から差し引く必要があります。
参考:No.3252 取得費となるもの|国税庁
参考:No.3261 建物の取得費の計算|国税庁
譲渡費用に含められる費用
譲渡費用は、不動産を売却するために直接かかった費用のことを指します。具体的には、不動産会社に支払った仲介手数料、売買契約書に貼付した印紙税、売却のために行った測量費、建物の解体費などが該当します。一方で、固定資産税や修繕費、管理費など、不動産の維持管理にかかった費用は譲渡費用には含まれないので注意が必要です。
参考:No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁
参考:No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁
所有期間で税率が変わる!短期と長期の違い
譲渡所得にかかる税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断されます。
- 短期譲渡所得:所有期間が5年以下の場合。税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)と高くなります。
- 長期譲渡所得:所有期間が5年を超える場合。税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)と、短期に比べて有利になります。
このように、あと数日で所有期間が5年を超えるというタイミングで売却すると、税額に大きな差が出ることがあります。売却を検討する際は、所有期間を意識することが大切です。
【節税】不動産売却で使える控除・特例制度

不動産売却で利益が出た場合でも、税金の負担を大幅に軽減できる様々な控除や特例制度が用意されています。特にご自身が住んでいたマイホームの売却では、手厚い優遇措置が受けられます。
これらの制度を知っているかどうかで納税額が大きく変わるため、利用できるものがないか必ず確認しましょう。ただし、これらの特例を適用するためには、確定申告が必須条件となります。
マイホーム売却なら3,000万円の特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除できるという非常に大きな特例です。例えば、譲渡所得が2,500万円だった場合、この控除を適用すれば課税対象となる所得が0円になり、所得税・住民税がかからなくなります。この特例を利用するためには、「自分が住んでいる家屋であること」や「親子や夫婦間での売買でないこと」など、いくつかの要件を満たす必要があります。
| 特例の名称 | 概要 | 主な適用要件 |
| 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる | 自分が住んでいる家屋の売却、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却など |
【関連記事】自宅売却で得られる特別控除の条件とは?「3,000万円控除」を徹底解説-【岡山県】不動産売却・査定・買取|後楽不動産の安心サポート
10年超所有のマイホームは軽減税率の特例
売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、前述の3,000万円特別控除を適用した後の譲渡所得に対して、さらに低い税率が適用される特例です。
通常、長期譲渡所得の税率は約20%ですが、この特例を使えば課税譲渡所得6,000万円以下の部分については約14.21%(所得税10.21%・住民税4%)にまで税率が下がります。3,000万円の特別控除と併用できるため、長年住んだマイホームを売却する際には非常に有利な制度です。
参考:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
特定のマイホームへの買い換え特例
マイホームを売却し、新たに別のマイホームに買い換えた場合に、売却した年の譲渡所得への課税を、将来新しいマイホームを売却する時まで繰り延べることができる制度です。この特例は課税が免除されるわけではなく、先送りにするものである点に注意が必要です。3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは選択制であり、併用はできません。どちらが有利になるかは、個々の状況によって異なります。
参考:No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁
参考:No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算|国税庁
売却損が出た場合の損益通算と繰越控除
マイホームの売却で損失(譲渡損失)が出てしまった場合に、その損失をその年の給与所得や事業所得など他の黒字の所得と相殺(損益通算)できる制度です。損益通算してもなお損失が残る場合は、翌年以降最大3年間にわたって損失を繰り越して控除(繰越控除)することができます。この特例を適用することで、所得税や住民税の還付を受けられる可能性があるため、損失が出た場合でも確定申告を検討する価値は十分にあります。
参考:No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
参考:No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
不動産売却の確定申告!具体的な手順と流れ

ここからは、実際に確定申告を行う際の具体的な手順を4つのステップに分けて解説します。全体の流れを把握することで、計画的に準備を進めることができます。特に書類の準備には時間がかかるものもあるため、早めに着手することがスムーズな申告の鍵となります。
手順1:必要書類を準備する
確定申告で最も重要なのが、必要書類を漏れなく揃えることです。売却した不動産の種類や、適用を受ける特例によって必要書類は異なります。売買契約書や領収書など、紛失しやすい書類もあるため、売却が決まった段階から意識的に保管しておくことが大切です。
具体的な書類リストは次の章で詳しく解説しますが、まずは税務署や国税庁のホームページで入手できる申告書様式や、法務局で取得する登記事項証明書など、どこで何を入手するのかを把握しておきましょう。
| 入手先 | 主な書類の例 |
| 税務署・国税庁HP | 確定申告書、譲渡所得の内訳書 |
| 法務局 | 登記事項証明書(登記簿謄本) |
| 自分で保管 | 売買契約書、仲介手数料などの領収書 |
参考:A4-1申告手続き(譲渡所得関係申告書添付書類)|国税庁
参考:各種証明書請求手続:法務局
手順2:譲渡所得の内訳書を作成する
譲渡所得の内訳書は、確定申告書に添付する書類で、不動産売却による所得の計算過程を詳細に記載するものです。売却価格、取得費、譲渡費用などを具体的に記入し、譲渡所得がいくらになったのかを計算します。
この書類は、税務署が売却内容を正確に把握するために非常に重要です。国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って数値を入力するだけで自動計算されるため、手書きよりも簡単で間違いも少なく作成できます。
手順3:確定申告書を作成する
譲渡所得の内訳書が完成したら、次はその内容を確定申告書に転記していきます。不動産の譲渡所得は「分離課税」という特殊な計算方法をとるため、通常の確定申告書(第一表・第二表)に加えて、「第三表(分離課税用)」という様式も必要になります。
給与所得などがある会社員の方でも、この第三表を追加で作成・提出する必要がある点を覚えておきましょう。こちらも「確定申告書等作成コーナー」を使えば、必要な様式が自動で選択され、計算もスムーズに行えます。
手順4:税務署へ申告・納税する
申告書類一式が完成したら、納税地の税務署に提出します。提出期間は、原則として不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
提出方法は、税務署の窓口へ直接持参するほか、郵送や時間外収受箱への投函も可能です。また、マイナンバーカードと対応するスマートフォンやICカードリーダライタがあれば、自宅から電子申告(e-Tax)も利用でき、非常に便利です。
納税は、申告期限と同じ3月15日までに行います。金融機関や税務署の窓口での納付のほか、口座振替やクレジットカード納付などの方法も選択できます。
確定申告の必要書類一覧

確定申告をスムーズに進めるためには、事前の書類準備が欠かせません。ここでは、不動産売却の確定申告において、基本的に必要となる書類と、特定の特例を利用する際に加えて必要となる書類を分けてご紹介します。早めにチェックリストとして活用し、漏れがないように準備を進めましょう。
全員が必要になる基本的な書類
以下は、不動産を売却して確定申告を行うすべての方が共通して必要となる書類です。特に売買契約書や領収書は、再発行が難しい場合もあるため、大切に保管してください。
| 書類名 | 主な入手先 | 備考 |
| 確定申告書(第一表、第二表、第三表) | 税務署、国税庁のHP | 第三表は分離課税用の様式です。 |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署、国税庁のHP | 譲渡所得の計算明細を記入します。 |
| 売買契約書の写し(購入時・売却時) | 自分で保管 | 取得費と売却価格を証明します。 |
| 譲渡費用や取得費の領収書の写し | 自分で保管 | 仲介手数料などの経費を証明します。 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 売却した不動産の情報を証明します。 |
| 本人確認書類(マイナンバーカード等) | 自分で用意 | マイナンバーの記載と本人確認に必要です。 |
【関連記事】不動産売却に必要な登記事項証明書(登記簿謄本)とは?取得方法や必要になるケースを解説-【岡山県】不動産売却・査定・買取|後楽不動産の安心サポート
特例の適用を受ける場合に別途必要な書類
3,000万円の特別控除など、節税効果の高い特例を適用するためには、上記の基本書類に加えて、その特例の要件を満たしていることを証明するための追加書類が必要になります。例えば、売却した不動産がマイホームであったことを証明するために、戸籍の附票の写しなどが必要となる場合があります。
どの特例を利用するかによって必要書類は異なるため、国税庁のホームページなどで必ず最新の情報を確認し、準備するようにしましょう。
不動産売却の確定申告に関するよくある質問

最後に、不動産売却の確定申告に関して、多くの方が疑問に思う点や不安に感じる点について、Q&A形式でお答えします。手続きを進める上での参考にしてください。
取得費が分からない場合はどうすればいいですか?
親から相続した不動産や、購入したのがかなり前で売買契約書を紛失してしまったなど、取得費を証明する書類が見つからないケースは少なくありません。このような場合、「売却価格の5%」を概算取得費として計上することが認められています。
しかし、実際の取得費が5%よりも大きい場合、この方法では譲渡所得が過大に計算され、納税額が増えてしまいます。まずは当時のパンフレットや預金通帳など、購入価額の参考になる資料がないか、できる限り探してみることが重要です。
相続した不動産を売却した場合の注意点は?
相続した不動産を売却した場合、所有期間は亡くなった被相続人がその不動産を取得した日から計算します。そのため、相続後すぐに売却したとしても、被相続人の所有期間が長ければ長期譲渡所得として低い税率が適用される可能性があります。
また、相続税を支払っている場合は、相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内にその不動産を売却すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を使える場合があります。
参考:No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁
参考:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
確定申告はいつまでに行えばいいですか?
不動産を売却した年の、翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行うのが原則です。この期間は毎年定められています。
例えば、2025年中に不動産を売却した場合、確定申告は2026年の2月16日から3月15日の間に行います。期限を過ぎてしまうとペナルティが発生する可能性があるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをお勧めします。
まとめ
不動産売却後の確定申告は、一見すると複雑で難しく感じるかもしれませんが、必要なケースを正しく理解し、手順に沿って一つずつ進めていけば、決して乗り越えられない壁ではありません。
特に、3,000万円の特別控除をはじめとする特例制度は、知っているだけで納税額を大きく減らせる可能性があるため、ご自身の状況に合うものがないか必ず確認しましょう。この記事が、あなたの確定申告に対する不安を少しでも和らげ、スムーズな手続きの一助となれば幸いです。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る