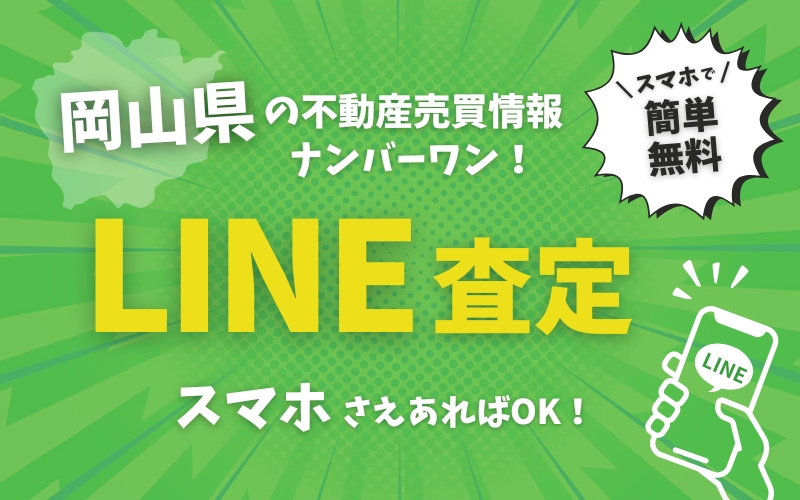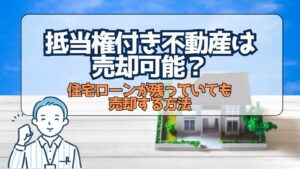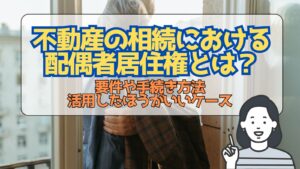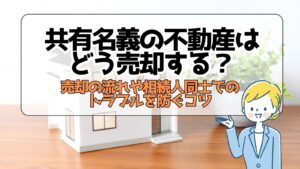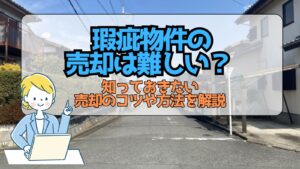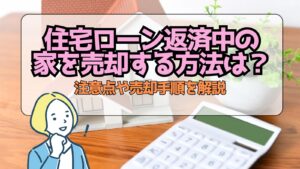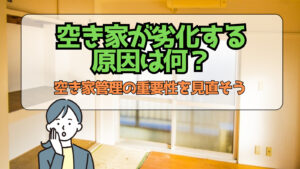2023年の法改正で空き家の固定資産税が最大6倍に!増税の仕組みと今すぐ取るべき対策
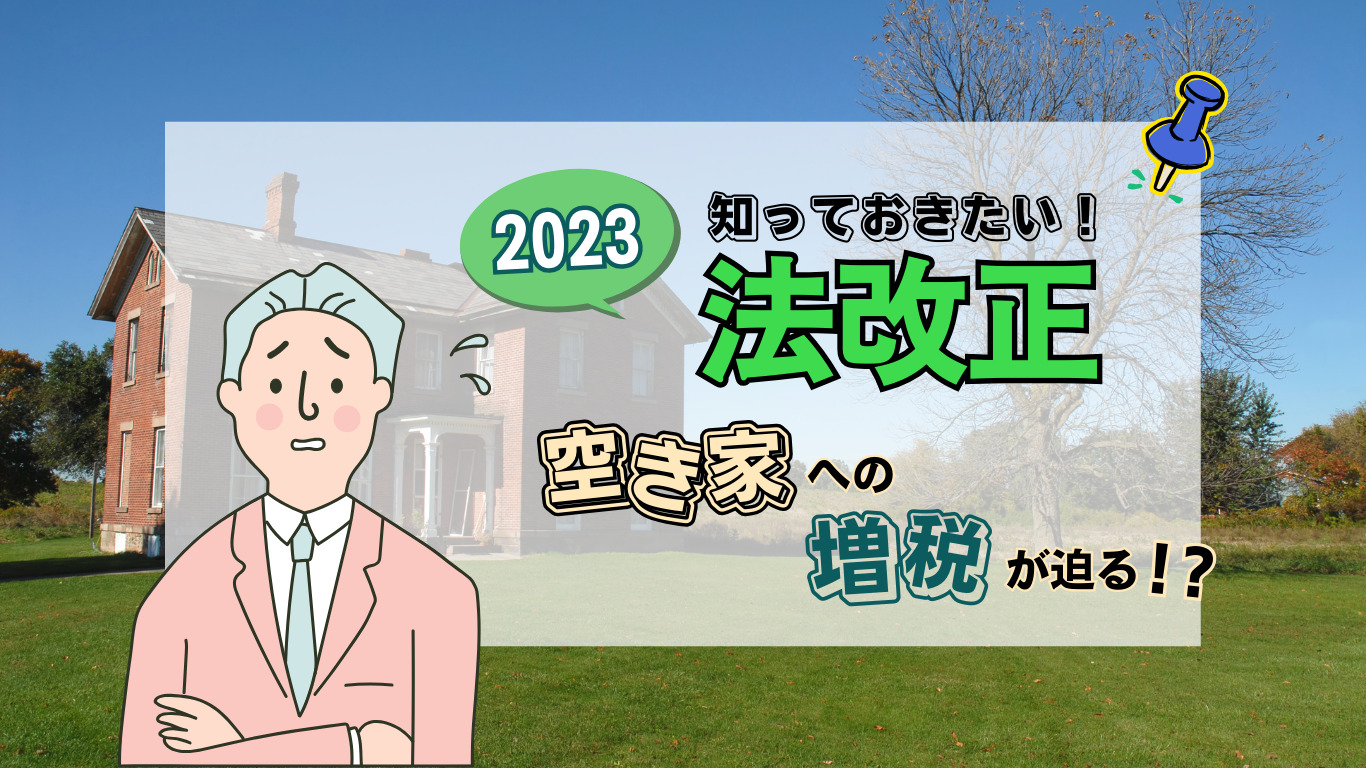
近年、日本全国で空き家の増加が深刻な問題となっています。これに伴い、2023年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、固定資産税の優遇措置が解除されるケースが拡大しました。
「空き家の固定資産税が4倍になる」「最大6倍に増える」という話を聞いて、不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、法改正による固定資産税の増額の仕組みや空き家所有者が取るべき対策について分かりやすく解説します。
この記事を監修した人

岩冨 良二
後楽不動産 売買事業部 係長
不動産業界歴26年のベテランで、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格を持つエキスパート。豊富な知識と実績でお客様から厚い信頼を得ており、売買事業部のエースとして活躍中。複雑な取引もスムーズにサポートし、最適な提案を行う頼れるプロフェッショナルでありながら、社内のムードメーカーとしても周囲を明るくする存在。
固定資産税は本当に4倍になるのか?

2023年12月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正により、空き家の管理が不十分な場合、固定資産税の負担が大幅に増加する可能性があります。
今回の法改正では、新たに「管理不全空家」のカテゴリーが設けられ、これに指定された空き家は「住宅用地特例」の適用が解除される可能性があります。住宅用地特例とは、住宅が建っている土地に適用される固定資産税の軽減措置のことで、これが解除されると、固定資産税が3~6倍に跳ね上がることになります。
住宅用地特例が解除されるとどうなる?
住宅用地特例が解除されると、以下のように課税額が変わります。
| 土地の種類 | 現行の固定資産税 | 特例解除後の固定資産税 | 増税幅 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 課税標準額が 1/6 に軽減 | 原則税率(1.4%)で課税 | 最大6倍 |
| 一般住宅用地(200㎡超) | 課税標準額が 1/3 に軽減 | 原則税率(1.4%)で課税 | 最大3倍 |
つまり、住宅用地特例が解除されると、これまで固定資産税が軽減されていた土地も通常の税率で課税されることになります。その結果、税負担が一気に跳ね上がることになるのです。
具体例:評価額1,000万円のケース
例えば、評価額1,000万円で、200㎡以下の土地に建つ空き家の場合、以下のように固定資産税額が変わります。
現行制度(住宅用地特例適用) → 固定資産税:約 2.3万円/年
特例解除後(管理不全空家に指定) → 固定資産税:約 14万円/年
年間の増額:+ 11.7万円(10年間で約 117万円の追加負担)
※固定資産税の計算式 /固定資産税額 = 評価額 × 課税標準額 × 税率(1.4%)
このように、住宅用地特例が解除されると、固定資産税が約6倍に増加し、長期間放置すれば負担額もどんどん膨れ上がることになります。
なぜ空き家の税金が上がるのか?

空き家の固定資産税が大幅に増額される背景には、政府が進める空き家対策の強化があります。近年、放置された空き家が増え続けており、これが地域に悪影響を及ぼしているため、行政が積極的に対応する必要が出てきました。特に、管理が不十分な空き家が周囲の安全や景観に悪影響を及ぼすケースが多く、自治体が早期に介入できる仕組みが整えられました。
今回の法改正では、「特定空家」に加えて「管理不全空家」の新設が行われ、一定の基準を満たさない空き家については住宅用地特例の適用が解除されることで、固定資産税が増額される仕組みになっています。
空き家を放置することによるリスク
空き家を放置すると、単に固定資産税が上がるだけではなく、地域や周辺住民に対するさまざまな悪影響を引き起こします。そのため、行政は「管理不全空家」や「特定空家」の指定を通じて、所有者に適切な管理を促す方針を打ち出しました。
1. 倒壊や火災のリスクがある
空き家は長期間放置されると、建物の劣化が進み、屋根や外壁が崩れやすくなる危険があります。特に、木造住宅の場合、湿気やシロアリの影響で柱や梁が腐食し、耐久性が低下することが多いです。台風や地震などの災害時に倒壊するリスクが高まるため、周囲の建物や通行人に危険を及ぼす可能性があります。
また、放置された空き家には放火のリスクもあります。建物の管理がされていないと、不審者が侵入しやすくなり、火災の原因となるケースが増えています。実際、全国各地で放火による空き家火災が報告されており、自治体も防火対策を強化しています。
2. 景観を損ね、周囲の不動産価値を下げる
管理されていない空き家は、外観が老朽化し、雑草が生い茂ることで地域の景観を著しく損なう原因になります。特に、住宅街や観光地では、空き家の放置が地域のイメージ低下につながり、周辺の不動産価値を押し下げる要因となります。
空き家の増加によって「売れにくいエリア」や「地価が下がるエリア」とみなされると、近隣の住民にとっても資産価値の低下という経済的な損失につながります。そのため、自治体は景観保全の観点からも、空き家の適切な管理を求めるようになっています。
3. 不法投棄や不審者の侵入による防犯面での問題
空き家は人の出入りがないため、不法投棄や不審者の侵入が発生しやすくなります。特に、都市部や郊外では、不法投棄によるゴミの放置が問題になっており、一度ゴミが捨てられると、さらに不法投棄が増える「負の連鎖」が起こりやすくなります。
また、管理されていない空き家は、犯罪の温床となる危険もあります。空き家を拠点として、不審者が住みついたり、犯罪の隠れ家として利用されるケースも報告されています。特に、夜間や人気の少ない場所にある空き家は、地域住民にとって治安悪化の要因となるため、早急な対応が求められています。
「管理不全空家」の新設とは?
これまで行政が指導・勧告できるのは、倒壊の危険性がある「特定空家」に限定されていました。しかし、今回の法改正により、特定空家になる前の段階でも行政が対応できるようにするため、「管理不全空家」のカテゴリーが新設されました。
「管理不全空家」に指定される条件
- 屋根や外壁の老朽化により、崩壊の危険がある
- 敷地内の雑草やゴミが放置され、景観を著しく損ねている
- 害虫・害獣の発生が確認され、近隣住民の生活に悪影響を与えている
- 不法投棄や不審者の出入りが頻繁に発生し、防犯上の問題が生じている
このような状態が認められると、自治体が空き家の所有者に対して指導・勧告を行うことが可能になります。
「管理不全空家」に指定されるとどうなる?
「管理不全空家」に指定されると、所有者には以下の影響があります。
- 自治体から指導・勧告を受ける
- 空き家の管理を求める通知が届き、改善が求められる。
- 一定期間内に対応しない場合、「特定空家」に指定される可能性がある。
- 住宅用地特例が解除され、固定資産税が増加
- 住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に増額する可能性がある。
- 「特定空家」に指定されると、さらに厳しい措置が取られる
- 勧告を無視すると、固定資産税の優遇が完全に解除される。
- 最終的に行政代執行(強制撤去)の対象となる可能性がある。
空き家を放置すると、税負担が増えるだけでなく、最悪の場合、強制撤去の費用まで請求されることになります。早めの管理や活用を検討することが重要です。
空き家所有者が取るべき対策

今回の法改正により、「とりあえず空き家をそのままにしておく」という選択肢はリスクが大きくなりました。空き家を適切に管理せず放置した場合、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が大幅に増加する可能性があります。また、管理不全空家や特定空家に指定されると、行政から指導や勧告を受けるだけでなく、最悪の場合は強制的に撤去されることも考えられます。
このようなリスクを避けるために、空き家所有者が取るべき具体的な対策について解説します。
定期的な管理を行い、空き家の劣化を防ぐ
空き家の適切な維持管理は、管理不全空家に指定されないための最も基本的な対策です。建物の劣化が進むと、修繕費用がかさむだけでなく、売却や賃貸の際の資産価値も低下してしまいます。
具体的な管理方法
- 定期点検を行う:最低でも 年に1~2回 は訪問し、屋根や外壁、窓ガラスの破損がないかを確認する。
- 庭や敷地を整備する:雑草の繁茂を防ぐために、定期的に除草作業を行う。害虫・害獣の発生を防ぐ効果もある。
- 空気の入れ替えをする:室内のカビや湿気対策として、定期的に窓を開け換気する。
- 設備の維持管理:雨どいや排水溝が詰まっていないか確認し、必要に応じて清掃する。
自身で管理が難しい場合は、空き家管理サービスを利用するのも一つの方法です。自治体や不動産会社が提供している管理代行サービスを活用することで、遠方に住んでいる場合でも適切な維持が可能になります。
空き家を売却する
「固定資産税の負担が増える前に売却したい」と考える所有者が増えています。空き家を放置すると、税負担だけでなく維持管理の手間や修繕費もかかるため、売却することでこれらの負担をすべて解消できます。
また、長期間使わない空き家は老朽化が進み、売却価格が下がる可能性があります。早めに売却することで、市場価値が高いうちに現金化でき、売却後は管理の手間も不要になります。
さらに、売却資金を活用すれば、新たな住まいや資産運用に充てることも可能です。不要な空き家を持ち続けるよりも、売却して有効活用する方が圧倒的にメリットが大きいといえます。
売却の流れ
- 現在の査定額を確認する:まずは不動産会社に査定を依頼し、空き家の価値を把握する。
- 売却の方針を決める:すぐに売却するのか、リフォームしてから売却するのかを検討する。
- 売却活動を開始する:不動産会社に仲介を依頼し、買い手を探す。
まずは現在の市場価値を確認し、最適な売却のタイミングを見極めましょう!
最近では、スマートフォンを使った簡単な査定サービスも増えており、自宅にいながら査定額を確認することができます。
手軽に査定額を知りたい方へ
「LINE査定」なら、スマートフォンで物件の情報を送るだけで、おおよその査定額を簡単に確認できます。
リノベーションや賃貸活用を考える
売却以外の選択肢として、空き家を賃貸物件として活用する方法があります。放置すれば固定資産税や維持費がかかる一方、賃貸にすれば家賃収入を得られ、資産として有効活用できます。
また、リノベーションを行うことで物件の価値を向上させ、より高い賃料で貸し出すことも可能です。古い住宅でも、適切な改修を施せば需要が高まり、安定した収益につながるケースもあります。
さらに、近年はシェアハウスや民泊など、空き家を活用する多様な選択肢も広がっています。「売るのはもったいない」「今は手放したくない」という場合は、リノベーションや賃貸活用を検討することで、空き家を資産として活かせる可能性があります。
活用の選択肢
- そのまま賃貸に出す:住宅として活用し、入居者を募集する。
- リノベーションを行い、価値を高める:設備を新しくすることで、賃貸や売却の可能性を広げる。
- シェアハウスや民泊として運用する:立地や物件の条件によっては、新たな活用方法として検討できる。
岡山県で中古住宅のリノベーションを検討している場合、「as rebra(アスリベラ)」を活用することで、物件購入からリフォーム・リノベーションまでワンストップでサポートを受けることができます。
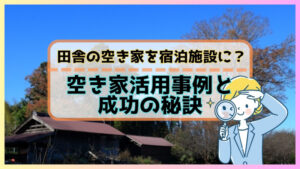
解体して更地にする
建物の老朽化が進んでいる場合、売却や賃貸よりも解体を検討するのも一つの選択肢です。解体すれば、管理の手間がなくなり、防犯面のリスクも軽減されます。
解体のメリット
- 管理や維持費用の負担をなくせる
- 倒壊や火災のリスクを回避できる
- 更地にすることで、新たな活用方法が広がる
ただし、更地にすると住宅用地特例の適用がなくなり、固定資産税が増額する点には注意が必要です。そのため、解体後にすぐに土地を売却する計画を立てることが重要になります。
また、多くの自治体では空き家の解体費用を補助する制度を設けています。補助金を活用することで、解体費用を抑えることができるため、自治体のホームページなどで事前に確認しておきましょう。

空き家対策を早めに行うべき理由

2023年の「空家等対策の推進に関する特別措置法」改正により、適切に管理されていない空き家の固定資産税が大幅に増加する可能性が高まりました。
新たに設けられた「管理不全空家」に指定されると、行政から指導・勧告を受け、改善されなければ「特定空家」に移行する恐れがあります。特定空家に指定されると住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍に増額するため、早めの対応が必要です。
さらに、今後は補助金の早期終了、解体業者の不足、空き家売却の難化といった問題も予想されるため、早めの空き家対策が求められます。
補助金の早期締め切りの可能性
現在、多くの自治体が空き家の解体や活用に関する補助金制度を設けており、これを活用すれば解体費用やリフォーム費用の一部を補助してもらうことができます。
しかし、補助金には自治体ごとの予算上限があり、申請が増えると年度途中で打ち切られる可能性があります。
また、申請には審査や書類準備が必要で、手続きに時間がかかるため、早めに進めることが重要です。さらに、補助金の支給額や対象条件は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
対策
- 自治体の補助金制度を早めに確認し、申請条件を把握する
- 解体やリフォームを検討している場合は速やかに見積もりを取得し、手続きを進める
解体業者の不足と費用の高騰
法改正により空き家対策の需要が高まると、解体業者への依頼が急増し、予約が取りづらくなる可能性があります。さらに、需要の増加に伴い解体費用が高騰することも考えられます。
また、需要が増えると「格安で解体できる」と謳う業者が現れ、手付金を受け取った後に連絡が取れなくなるといった詐欺の発生が懸念されます。そのため、解体を依頼する際は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
対策
- 早めに解体業者へ相談し、事前に見積もりを取得する
- 自治体や不動産会社を通じて信頼できる業者を紹介してもらう
- 極端に安い価格を提示する業者には注意し、複数の業者から相見積もりを取る
売却困難と価格の下落リスク
法改正により税負担が増える前に空き家を売却しようと考える所有者が増えることが予想されます。その結果、市場に売却物件が大量に出回り、中古住宅市場が飽和状態になる可能性があります。
供給が増えれば競争が激化し、売却価格の下落リスクが高まるため、希望価格で売却できないケースが増えるかもしれません。また、買い手にとっては選択肢が増えるため、価格交渉が有利になり、相場よりも低い価格での取引が発生しやすくなる可能性があります。
さらに、売却希望者が増えることで、売れ残るリスクも高まります。市場の動向を見極めながら、早めの売却計画を立てることが重要です。
対策
- 売却を検討している場合は、税負担が増える前に市場価値を把握し、早めに動く
- 不動産会社に相談し、適正価格での売却戦略を立てる
- オンライン査定を活用し、簡単に売却価格の目安を知る
まとめ
2023年の法改正により、管理されていない空き家の固定資産税が最大6倍に増額される可能性が高まりました。特に、「管理不全空家」に指定されると固定資産税の優遇措置が解除され、放置すれば「特定空家」になり、さらに厳しい措置が取られるリスクがあります。
空き家所有者が取るべき行動は以下の通りです。
- 売却を検討(税負担が増える前に手放す)
- 適切な管理(「管理不全空家」指定を防ぐ)
- 賃貸・リノベーションで活用(収益化する選択肢)
- 解体を検討(税負担や管理の手間をなくす)
また、全国的に空き家対策が進む中、補助金の早期終了や解体業者の不足、売却物件の増加による価格下落なども予想されます。後回しにせず、今すぐ動き出すことが重要です。
まずは現在の価値を知ることが第一歩!
「売却するか、活用するか、解体するか」を決めるためには、まずは空き家の市場価値を把握することが大切です!