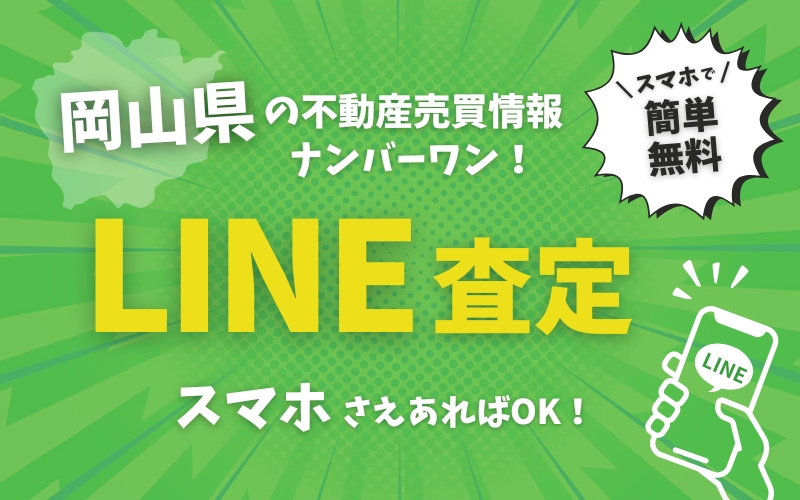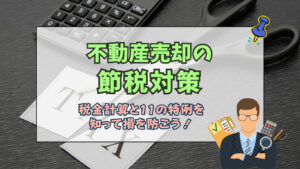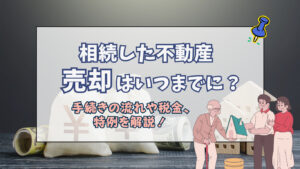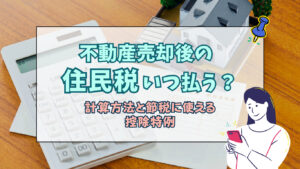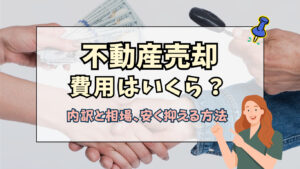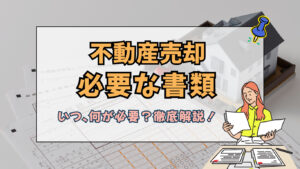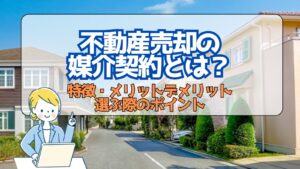不動産売却の税金はいくら?計算方法と使える特例をわかりやすく解説
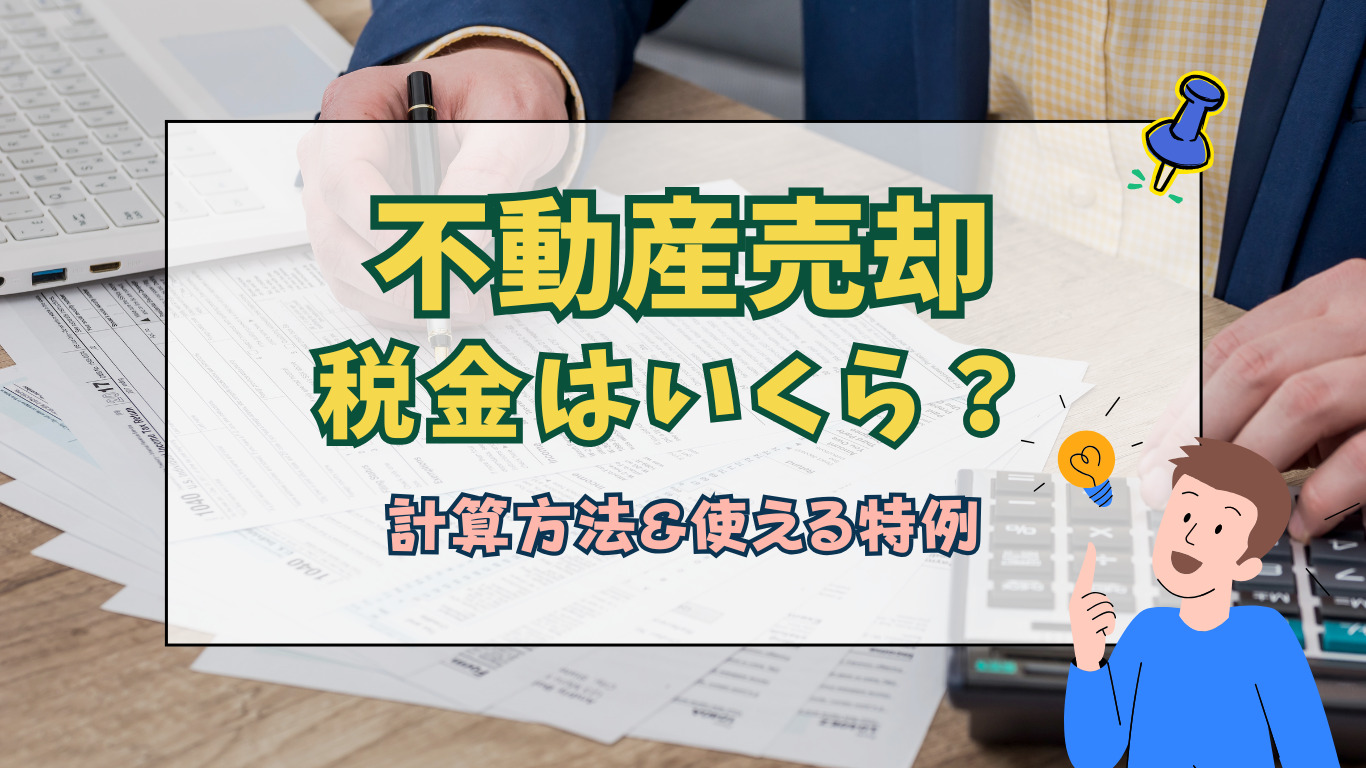
不動産を売却すると、多くの場合で税金が発生します。しかし、「どんな税金が」「いくら」「いつまでに」必要なのか、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。特に、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合の税金は高額になることもあり、知らずにいると「思ったより手元にお金が残らなかった」という事態になりかねません。
この記事では、不動産売却にかかる税金の基本から、複雑な計算方法、そして賢く節税するための特例まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
不動産売却でかかる税金は4種類

不動産を売却する際には、主に4種類の税金がかかります。売却で利益が出た時にだけかかる税金と、手続きの過程で必ずかかる税金があります。まずは全体像を把握しましょう。
| 税金の種類 | 課税対象 | 納税のタイミング |
| 譲渡所得税(所得税・住民税) | 不動産を売却して得た利益(譲渡所得) | 売却した翌年の確定申告時 |
| 印紙税 | 不動産売買契約書 | 契約時 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消などの登記手続き | 決済・引き渡し時 |
| 消費税 | 不動産会社に支払う仲介手数料など | 決済・引き渡し時 |
売却益にかかる「譲渡所得税(所得税・住民税)」
不動産売却における税金の中心となるのが、この譲渡所得税です。これは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金で、「所得税」と「住民税」を合わせたものを指します。給与所得などとは別に計算される「分離課税」という方式がとられるため、会社員の方でも別途確定申告が必要です。もし売却によって利益が出なかった場合、つまり譲渡所得がゼロかマイナスの場合は、譲渡所得税はかかりません。
契約書作成時の「印紙税」
印紙税は、不動産売買契約書などの課税文書を作成した際に課される税金です。契約書に記載された売買金額に応じて税額が決められており、収入印紙を契約書に貼り付けて消印をすることで納税します。例えば、売買価格が1,000万円超5,000万円以下の場合、本則では2万円の印紙税がかかりますが、現在は軽減措置が取られており1万円となっています(2027年3月31日まで)。
登記手続きの「登録免許税」
売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、金融機関が設定した抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」が必要です。この登記手続きの際に課されるのが登録免許税です。税額は不動産1つにつき1,000円で、手続きを依頼する司法書士への報酬と合わせて支払うのが一般的です。
仲介手数料などの「消費税」
不動産会社に仲介を依頼して売却した場合、成功報酬として支払う仲介手数料には消費税がかかります。個人の売主がマイホームなどを売却する場合、土地や建物自体は非課税ですが、不動産会社や司法書士といった事業者へ支払うサービス料には消費税が課されると覚えておきましょう。
メインの税金!譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は金額が大きくなりやすいため、計算の仕組みをしっかり理解しておくことが重要です。計算は大きく4つのステップに分かれています。順を追って確認していきましょう。
STEP1:譲渡所得を計算する
まず、税金の計算の基礎となる「譲渡所得」を求めます。譲渡所得は、単純な売却価格そのものではなく、売却価格から不動産の購入にかかった費用や売却にかかった経費を差し引いた、純粋な利益部分を指します。
計算式:譲渡所得 = 譲渡収入金額 – (取得費+譲渡費用)
- 譲渡収入金額:不動産の売却代金です。
- 取得費:売却した不動産の購入代金や、購入時にかかった仲介手数料、登記費用などの合計額です。建物の場合は、年数の経過による価値の減少分(減価償却費)を購入代金から差し引いて計算します。
- 譲渡費用:売却時にかかった仲介手数料や印紙税、測量費など、売るために直接かかった費用のことです。[優松5]
参考:No.3202譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁
STEP2:所有期間を確認し税率を判断する
次に、算出した譲渡所得にかける税率を確認します。この税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。所有期間は、不動産を売却した年の1月1日時点で判断される点に注意が必要です。
| 所有期間の区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
ご覧の通り、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が約2倍も変わります。例えば、2020年4月に購入した不動産を2025年10月に売却する場合、実際の所有期間は5年を超えていますが、売却した年である2025年の1月1日時点ではまだ5年以下です。そのため、この場合は「短期譲渡所得」に区分されます。長期譲渡所得の税率を適用するには、2026年1月1日以降に売却する必要があります。
参考:No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁
参考:No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|国税庁
参考:No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁
STEP3:特別控除を適用する
不動産売却には、税負担を軽減するための様々な特例(特別控除)が用意されています。もし利用できる特例があれば、STEP1で計算した譲渡所得から控除額を差し引くことができます。この結果、課税対象となる金額(課税譲渡所得)が算出されます。
計算式:課税譲渡所得 = 譲渡所得-特別控除額
例えば、マイホームの売却で利用できる「3,000万円の特別控除」を使えば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。譲渡所得が3,000万円以下であれば、この特例を使うことで課税譲渡所得は0円になり、結果として譲渡所得税はかかりません。
参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
参考:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁
STEP4:税額を計算する
最後に、STEP4で算出した課税譲渡所得に、STEP3で確認した税率を掛け合わせ、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算することで、納めるべき税額が確定します。
計算式:譲渡所得税額 = 課税譲渡所得 × 税率 + 復興特別所得税
このように、一つ一つのステップを踏むことで、複雑に見える税金計算もご自身で行うことが可能です。
参考:No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁
参考:土地や建物を売ったとき|国税庁
【具体例】譲渡所得税の計算シミュレーション

ここでは、具体的な数字を使って税額がいくらになるのかシミュレーションしてみましょう。
【共通条件】
- 譲渡収入金額:4,000万円
- 取得費:3,000万円
- 譲渡費用:150万円
まず、譲渡所得を計算します。
所有期間5年以下(短期譲渡所得)の場合
所有期間が5年以下のため、税率は39.63%です。
所有期間5年超(長期譲渡所得)の場合
所有期間が5年を超えるため、税率は20.315%です。
マイホームの特例を使う場合
この物件がマイホームで、所有期間が5年超、かつ「3,000万円の特別控除」の適用要件を満たす場合を考えます。
課税譲渡所得が0円以下になるため、税額は0円となります。このシミュレーションから、特例を使えるかどうかで税負担が大きく変わることが分かります。
必ず知っておきたい!不動産売却で使える節税特例

不動産売却の税金を抑えるためには、特例をうまく活用することが不可欠です。ここでは代表的な特例をご紹介します。ただし、それぞれの特例には細かい適用要件があり、併用できない場合もあるため、利用を検討する際は国税庁のホームページで最新の情報を確認するか、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
マイホーム売却で使える3,000万円の特別控除
自分が住んでいた家(マイホーム)を売却した場合、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。非常に効果の大きい制度ですが、住まなくなってから3年目の年末までに売却すること、親子や夫婦間での売買ではないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
【関連記事】自宅売却で得られる特別控除の条件とは?「3,000万円控除」を徹底解説-【岡山県】不動産売却・査定・買取|後楽不動産の安心サポート
所有期間10年超で使える軽減税率の特例
売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えているマイホームを売却した場合、課税譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、通常の長期譲渡所得の税率(20.315%)よりも低い10%(所得税のみ)の軽減税率が適用されます。この特例は、前述の3,000万円特別控除と併用することが可能です。
| 課税譲渡所得金額 | 所得税 |
| 6,000万円以下の部分 | 10% |
| 6,000万円を超える部分 | 15% |
(注)上記は所得税率のみ。別途住民税と復興特別所得税が課税されます。
相続した空き家を売却する場合の3,000万円特別控除
亡くなった親などが一人で住んでいた家(空き家)を相続し、一定の要件を満たした上で売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。相続開始から3年後の年末までに売却することや、売却代金が1億円以下であることなどの条件があります。
【関連記事】相続した不動産の売却にかかる費用はどれくらい?登記費用・仲介手数料・解体費用・各種税金について解説-【岡山県】不動産売却・査定・買取|後楽不動産の安心サポート
参考:No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
特定のマイホームを買い換えた場合の特例
マイホームを売却し、新たにマイホームを買い換える場合に利用できる特例です。売却した年の1月1日時点で所有期間・居住期間がともに10年超であることなど、一定の要件を満たせば、譲渡益への課税を将来に繰り延べることができます。これは税金が免除されるわけではなく、次に買い換えた家を売却する時まで先送りされる制度である点に注意が必要です。
参考:No.3355特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁
売却で損失が出た場合の損益通算と繰越控除
不動産を売却して利益が出るどころか、損失(譲渡損失)が出てしまった場合にも使える特例があります。一定の要件を満たすマイホームの売却で出た損失は、その年の給与所得や事業所得など、他の所得から差し引くこと(損益通算)ができます。それでも引ききれない損失は、譲渡の年の翌年以後3年間にわたって繰り越して控除(繰越控除)することが可能です。これにより、所得税や住民税の還付を受けられる場合があります。
参考:No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
参考:No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁
不動産売却後の手続きと税金の納税方法

税金の計算ができたら、次は申告と納税です。手続きの期限や流れを把握し、忘れずに済ませましょう。
譲渡所得税はいつまでに納める?
譲渡所得税の申告と納税は、不動産を売却した翌年に行います。申告期間は原則として2月16日から3月15日までで、この期間内に確定申告書を税務署に提出し、納税を完了させる必要があります。住民税については、確定申告をすれば自動的に計算され、その年の6月頃に納税通知書が送られてきます。
参考:No.3102 譲渡所得の申告期限|国税庁
参考:不動産売却は翌年の住民税にどう影響する?かからないケースとは|ナカジツの「住まいのお役立ち情報」
確定申告の準備と必要書類
確定申告には、以下の書類が必要となります。早めに準備を始めましょう。
- 確定申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 売却した不動産の売買契約書のコピー
- 売却した不動産の購入時の売買契約書のコピー
- 売却時および購入時にかかった費用の領収書
- 登記事項証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- (特例を利用する場合)各特例の適用に必要な書類
参考:A4-1申告手続き(譲渡所得関係申告書添付書類)|国税庁
参考:国税庁-資産税関係添付書類等一覧表(令和5年分用)
税金の納付方法
所得税の納付には、いくつかの方法があります。
- 現金納付:金融機関や税務署の窓口で納付書を使って支払う方法です。
- 振替納税:自身の銀行口座から自動で引き落としてもらう方法です。事前に手続きが必要です。
- クレジットカード納付:専用サイトを通じてクレジットカードで支払う方法です。
- コンビニ納付:QRコードを使ってコンビニエンスストアで支払う方法です(30万円以下の場合)。
参考:G-2国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)|国税庁
参考:G-2-6コンビニ納付(QRコード)|国税庁
不動産売却の税金に関するよくある質問

最後に、不動産売却の税金に関して多くの方が疑問に思う点についてお答えします。
取得費がわからない場合はどうする?
親から相続した不動産や、購入時期が古く売買契約書が見つからない場合など、取得費が不明なケースがあります。その場合は、「売却価格の5%」を概算の取得費として計算することが認められています。しかし、実際の取得費が5%より高い場合、この方法では譲渡所得が過大に計算され、税金が高くなってしまいます。契約書以外にも、購入時のパンフレットや住宅ローン契約書などが取得費の証明になる場合もあるため、諦めずに探してみましょう。
参考:No.3258 取得費が分からないとき|国税庁
参考:No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁
相続した不動産の所有期間はどうなる?
相続によって取得した不動産の所有期間は、相続が発生した日から数え始めるのではありません。亡くなった方(被相続人)がその不動産を取得した日から通算して計算します。例えば、親が30年前に購入した実家を相続してすぐに売却した場合でも、所有期間は「30年超」となり、長期譲渡所得の税率が適用されます。
【関連記事】不動産を相続した際にかかる税金はどれくらい?-【岡山県】不動産売却・査定・買取|後楽不動産の安心サポート
参考:No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁
参考:【確定申告書等作成コーナー】-相続や贈与によって取得した資産の取得の時期
確定申告をしないとどうなる?
譲渡所得があるにもかかわらず確定申告を怠ると、本来納めるべき税金に加えて、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されてしまいます。特に、税務署は不動産の登記情報を把握しているため、無申告は見つかる可能性が非常に高いです。特例を利用して納税額が0円になる場合でも、その特例の適用を受けるためには確定申告が必須です。利益が出た場合は、必ず期間内に申告を行いましょう。
参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
参考:不動産等を売却した方へ|令和6年分確定申告特集
まとめ
不動産売却にかかる税金は、種類や計算方法が複雑で難しく感じられるかもしれません。しかし、その仕組みを正しく理解し、ご自身の状況に合った特例を活用することで、税金の負担を大きく軽減できる可能性があります。
まずは、ご自身の不動産の取得費やおおよその売却価格を把握し、譲渡所得がどれくらいになるか試算してみることから始めましょう。もし計算や特例の適用要件で不明な点があれば、専門家である税理士や税務署に相談することをお勧めします。
LINE査定サービス
スマホひとつで、岡山県内の不動産をどこからでも簡単に査定可能。
「とりあえず査定額を知りたい」という方にもぴったりです。その後のご相談もすべてLINEでスムーズにやり取りできるので、安心してご利用いただけます。
>>詳細を見る